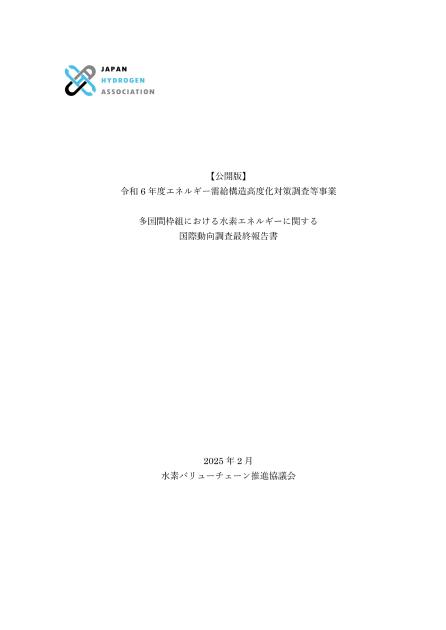令和 6 年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業多国間枠組における水素エネルギーに関する国際動向調査最終報告書
報告書概要
この報告は、令和6年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業として、多国間枠組における水素エネルギーに関する国際動向について調査した報告書である。
水素エネルギーは21世紀のエネルギー転換において中心的役割を担う可能性を秘めており、地球環境の保全とエネルギーの持続可能な利用を結び付け、新たな産業を創出することが期待されている。我が国のエネルギー政策では、水素を燃料や原料として活用し、運輸、発電、産業といった多岐にわたる分野で脱炭素化を進める重要なエネルギー源として位置付けられている。
本調査では、国際水素・燃料電池パートナーシップ(IPHE)における運営委員会会議、水素認証タスクフォース、水素環境影響評価など、水素エネルギー関連の国際会議を通じて得られた情報を包括的に整理した。これらの会議では、温室効果ガスの排出量を算定するための手法、認証スキームの相互承認を実現するための必要条件、再生可能エネルギーの適用要件、貿易ルール、各種規制に関する議論が精力的に進められた。
また、IPHE、IEA(国際エネルギー機関)、IRENA(国際再生可能エネルギー機関)といった国際機関のレポートを基に、米国、EU、ドイツ、イギリス、韓国などの水素主要国における水素政策の進展や規制動向に関する詳細な調査を実施した。特に、クリーン水素認証スキームの国際的調和を目指す取り組みが焦点となっており、今後の国際的な水素市場の基盤づくりに重要な示唆を与えている。
調査の結果、水素の普及には国際的な協力と連携が不可欠であることが明らかとなった。各国の異なる制度や基準を調和させるためには、技術的な情報共有のみならず、規制や市場の枠組みについても緊密な協力が求められる。これにより、水素の取引や流通の円滑化が進み、グローバル市場の形成が促進されると考えられる。
日本国内では、水素社会推進法が施行され、水素の社会実装が具体性を増している。価格差支援を通じた水素導入が現実的な選択肢として浮上しており、水素エネルギーの普及を経済的にも後押しする枠組みが整備されつつある。また、エネルギー基本計画において水素を次世代エネルギーの柱として位置付ける政策が強調されており、グリーン水素の生産技術や関連インフラの高度化、地域経済や雇用創出への貢献を目指した取り組みが進められている。