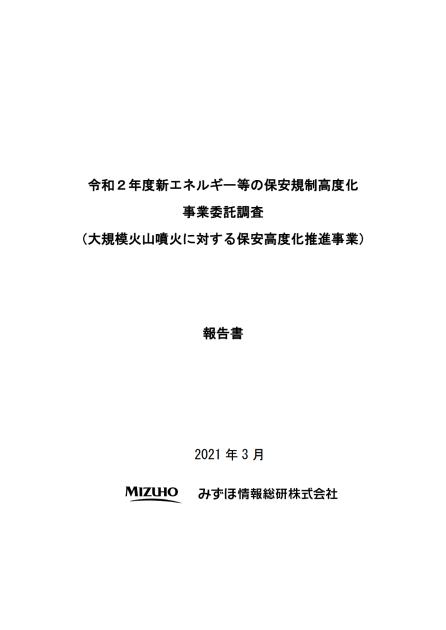令和2年度新エネルギー等の保安規制高度化事業委託調査(大規模火山噴火に対する保安高度化推進事業)報告書
報告書概要
この報告は、富士山噴火による降灰が電力設備に与える影響について書かれた報告書である。経済産業省が設置した検討ワーキンググループにより、令和3年に実施された調査研究の成果をまとめたものとなっている。
報告書では、日本国内の111の活火山のうち48火山で噴火警戒レベルが設定されており、特に富士山噴火をモデルケースとして電力設備への影響を詳細に分析している。降灰による電力設備への影響については、発電設備では火力発電のガスタービン吸気フィルターへの火山灰詰まりによる機能低下、配電線・送電線では碍子の絶縁性能低下による停電、変電所でも同様の絶縁低下が問題となることが明らかにされている。
降灰シミュレーションに基づく具体的な影響検討では、富士山噴火時の降灰パターンを3つのケースに分けて分析が行われた。配電線については降雨時3mm以上の降灰で停電リスクが高まり、送電線では27万7千基の鉄塔のうち約1万基が影響を受ける可能性があることが示されている。変電所では1,157箇所のうち約100箇所で影響が想定される結果となっている。
発電設備への影響については、火力発電設備で最大42%の供給量低下、太陽光発電設備では発電量がほぼゼロになる可能性が指摘されている。東京電力管内では噴火15日後に定格出力の約65%まで低下し、中部電力管内では約95%程度の維持が可能であることが試算されている。
初動対応としては、気象庁の降灰予報に基づく要員確保の準備、道路管理者との連携による復旧ルートの確保が重要である。事後対策では、作業可能条件確認後の順次復旧、電源車による災害拠点への電力供給が必要とされている。特に30mm以上の降灰地域では道路啓開が必要となり、復旧作業の長期化が懸念される。
克服すべき課題として、道路管理者や自治体との緊密な連携、気象庁による適切な降灰予報の提供、災害拠点との連携体制構築が挙げられている。また、電力需給逼迫時には産業用電力需要抑制や国民への節電要請、他電力エリアからの融通電力確保が必要となる可能性が示されている。