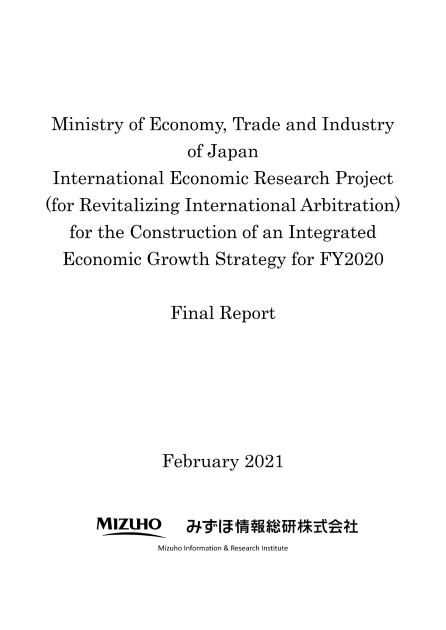令和2年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(国際仲裁活性化に向けた調査事業)最終報告書(英語)
報告書概要
この報告は、日本の国際仲裁活性化に関する経済産業省の国際経済研究プロジェクトについて書かれた報告書である。近年、海外投資の増加に伴い、企業間紛争解決手段として国際仲裁の需要が世界的に高まっている。シンガポール国際仲裁センター(SIAC)では2007年の86件から2019年の416件へと大幅に増加しているが、日本の仲裁機関が扱う国際仲裁案件数は増加していない。この原因として、海外企業が日本を第三国仲裁地として認識していないこと、また日本企業における国際仲裁への認識不足が挙げられる。
各国の仲裁機関の取り組みを調査した結果、案件数増加のためには仲裁機関自体の情報発信が不可欠であることが判明した。ICC、SIAC、HKIACなどは多言語でのウェブサイト運営や海外プロモーション活動を積極的に展開している。また中国や韓国の仲裁機関も国際的プレゼンスを高めており、ウェブサイトの多言語化や仲裁人の国際化を推進している。
将来の国際仲裁動向については、地域ごとに特色がある。欧州のICCやLCIAではエネルギー分野が大きな割合を占め、北米のAAA/ICDRでは科学・ヘルスケア分野の大型案件が増加している。東南アジアのSIACやHKIACでは企業法務、貿易、海事分野の案件が多く、中国や韓国では貿易業に加えて電子機器やIT関連プロジェクトの仲裁が増加している。
COVID-19パンデミックの影響により、多くの仲裁機関がオンライン仲裁手続きを推進し、ウェビナーによるセミナー開催が活発化した。オンライン審理は今後の「ニューノーマル」となることが予想される。
日本企業に対する推奨戦略として、特に中小企業における紛争解決条項の重要性や仲裁制度への理解不足が課題として指摘されている。海外企業に対しては、日本の仲裁地としての認知度の低さと英語を含む多言語対応の不備が問題となっている。これらの課題解決のため、積極的な情報発信と啓発活動、具体的な事例紹介、相談窓口の設置などが必要であると結論づけられている。