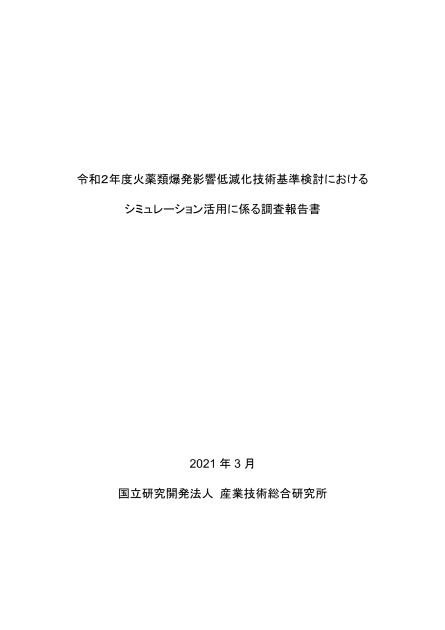令和2年度火薬類爆発影響低減化技術基準検討におけるシミュレーション活用に係る調査報告書
報告書概要
この報告は、火薬類取締法の技術基準制定における野外実験に代わる評価手法としてのシミュレーション活用可能性について調査した報告書である。経済産業省では従来、火薬類の爆発影響を評価するため実際に火薬類を爆発させる野外実験を実施してきたが、場所や予算面での制約があることから、近年のシミュレーション技術の進展を踏まえ、より効率的かつ信頼性のある技術基準策定手法の確立を目指した調査が行われた。
調査は三つの観点から実施された。第一に、火薬類の爆発影響を評価可能なシミュレーションソフトについて調査が行われ、Ansys-AUTODYN、Ansys-LS-DYNA、IMPETUS Afea Solverが代表的なソフトとして特定された。これらのソフトは爆轟生成ガスの状態方程式であるJWL状態式を利用でき、爆風圧、地盤振動、飛散物の影響評価が可能であることが確認された。第二に、平成元年度以降のシミュレーション活用状況について調査が実施され、平成7年度から16年度にかけて爆風評価を中心としたシミュレーションが段階的に発展してきたことが明らかになった。第三に、火薬類取締法の技術基準制定における具体的なシミュレーション活用可能性について検討された。
シミュレーション活用における課題として、爆発現象の複雑性、計算コストの高さ、妥当性検証の困難性などが指摘された。爆轟現象は高温高圧の衝撃波を伴い、材料の状態方程式や構成則のパラメータ設定が評価精度に大きく影響するため、国内の火薬類に適した状態方程式の構築が必要である。また、大規模計算では格子幅を小さくすると計算時間が長くなり、実用的な制約が存在することも明らかになった。
委員会での議論では、シミュレーションのみによる技術基準策定は困難であり、野外実験との併用が必要であることが確認された。費用面では野外実験が2千万から2千5百万円に対し、シミュレーションは1千万から3千万円と必ずしも安価ではないが、野外実験回数の削減により全体的な費用効率化が期待できると評価された。今後の方向性として、シミュレーションの適用可能性を事前に十分検討し、技術基準策定に要求される精度を確保できる場合にのみ活用するという慎重なアプローチが提案された。