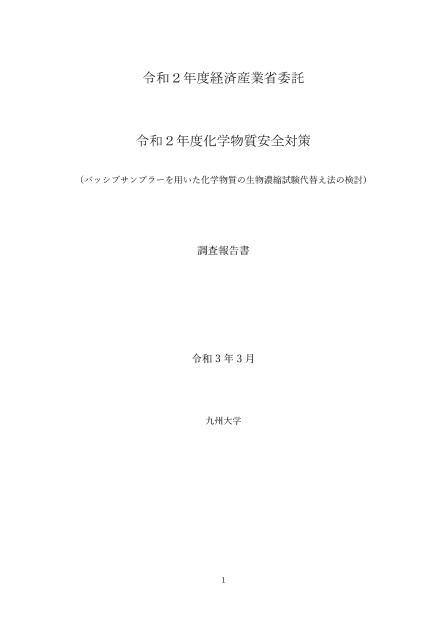令和2年度化学物質安全対策(パッシブサンプラーを⽤いた化学物質の⽣物濃縮試験代替え法の検討)調査報告書
報告書概要
この報告は、化学物質の生物濃縮試験の代替手法としてパッシブサンプラー(SPMD)の有効性について検討した研究報告書である。
現在、化審法では新規化学物質の蓄積性評価において魚類を用いた濃縮試験が必要とされているが、この手法は大規模な設備、高コスト、長時間を要し、個体差や実験条件による結果のばらつきが問題となっている。また動物愛護の観点からも実験生物数の削減が求められている。このため、生物濃縮試験に代わる代替手法の開発が急務とされている。
本研究では、ポリエチレン製半透膜チューブにトリオレインを封入したSemi permeable membrane device(SPMD)を用いて、log Pow 4から5の範囲にある4種類の塩素化ベンゼン系化学物質について検討を行った。具体的には1,3,5-トリクロロベンゼン、1,2,4,5-テトラクロロベンゼン、ペンタクロロベンゼン、ヘキサクロロベンゼンを被験物質として選定し、コイとSPMDを同一条件下で28日間の取込み試験および28日間の排泄試験を実施した。
実験の結果、魚体から得られた脂質補正生物濃縮係数(BCF)とSPMD試験から得られた脂質補正BCFの対数値には非常に良好な相関関係が認められた。この結果は、被検物質のlog Powが4から5の範囲であれば、SPMDを用いて魚類試験に代替してBCFを予測できる可能性が高いことを示している。
さらに、アントラセンを用いたSPMDの蓄積排泄実験では、化学物質がトリオレインだけでなくポリエチレン膜にも蓄積することが明らかとなった。濃度変化から求めた吸収・排泄速度によるシミュレーション結果から、アントラセンはSPMD膜に蓄積した後、膜の孔を介してトリオレインに移行すると考えられた。
今後の課題として、log Pow 3から5の範囲にある特性の異なる物質を用いたさらなる検証が必要であり、既知の化学物質についてもSPMDによる検証を加える必要がある。また、より高いlog Pow値を持つ難水溶性物質に対する代替試験法の開発も求められている。SPMD法の実用化に向けては、ポリエチレン膜における化学物質蓄積についても十分な注意が必要である。