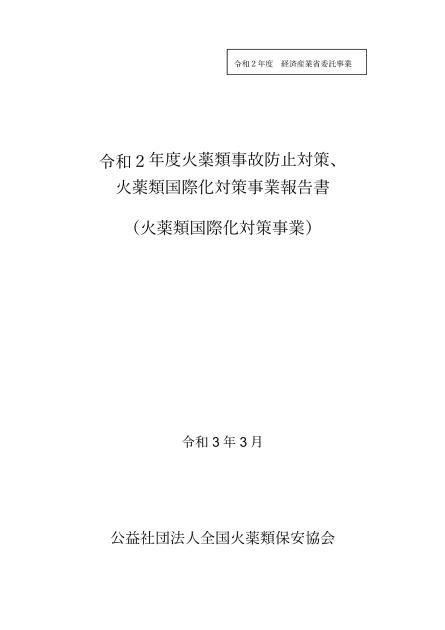令和2年度火薬類事故防止対策、火薬類国際化対策事業(火薬類国際化対策事業)報告書
報告書概要
この報告は、令和2年度に経済産業省の委託を受けて実施された火薬類国際化対策事業について書かれた報告書である。
本事業では、火薬類の保安規制の国際化への対応として、国連危険物輸送専門家小委員会(UNSCETDG)及び国連分類調和専門家小委員会(UNSCEGHS)における火薬類関連の各国提案文書を検討し、我が国の意見を国際会議に反映させることを目的としている。令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、当初予定されていた6月開催の第1回委員会は延期となり、11月末から12月初旬にかけて第57回UNSCETDG及び第39回UNSCEGHSがハイブリッド開催で実施された。
火薬類国際化対応委員会は、小川輝繁委員長をはじめとする学識経験者、関係団体代表者等で構成され、第1回及び第2回委員会を書面開催、第3回委員会をリモート開催により実施した。また、国際会議への派遣者として薄葉州委員(産業技術総合研究所)がリモート参加し、火薬作業部会での議論にも参加した。
審議された主要な火薬類関連事項として、試験シリーズ6の見直し、試験シリーズ8の改善、試験マニュアルの見直し、UN標準雷管、爆発物の包装要件、電子雷管、ニトロセルロースの安定性試験等が含まれている。特に試験シリーズ8については、硝酸アンモニウムエマルション等の分類に用いられるケーネン試験の問題点が継続的に議論されており、最小燃焼圧力試験との併用が検討されている。電子雷管については新たなUN番号の設定が採択され、国内法令への反映も進められている。ニトロセルロースの安定性試験については、2015年の中国天津での爆発事故を受けて提案されたベルクマン・ユンク試験及びメチルバイオレット紙試験の手順が試験判定基準マニュアルに追加された。報告書には各提案文書の概要、審議結果、委員会の議事録等が詳細に記載されており、火薬類の国際規制動向を把握するための重要な資料となっている。