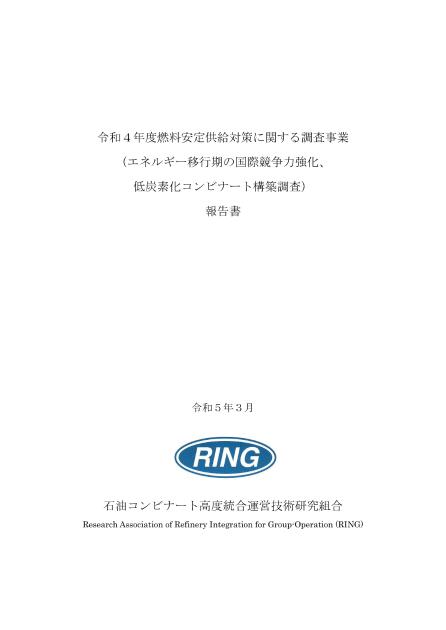令和4年度燃料安定供給対策に関する調査事業(エネルギー移行期の国際競争力強化、低炭素化コンビナート構築調査)報告書
報告書概要
この報告は、エネルギー移行期における日本の石油コンビナートの国際競争力強化と低炭素化について書かれた報告書である。
世界的な脱炭素の流れと2050年カーボンニュートラル宣言を受けて、日本の石油コンビナートが直面する新たな課題と対応策を調査している。ロシア経済制裁下で輸出競合相手となる中国、中東等のアジア圏の大規模工業団地や、米国第二次シェール革命の進展がアジア圏の国際競争に及ぼす影響を分析し、脱ロシアエネルギー政策に腐心する欧州の実態調査を実施した。
海外調査では、アジア圏において中国が第14次5カ年計画で2030年までに再生可能エネルギー発電容量500GWを目標とし、7大コンビナートの建設稼働が進展していることを確認した。インドでは2070年ネットゼロ目標を掲げ、リライアンス社による石精石化インテグレーションの進化が注目される。中東諸国では豊富な太陽光や風力資源を活用したグリーン水素投資が本格化している。米国では第二次シェール革命によりエタンを原料とするエチレン分解炉新増設が進み、エンタープライズ社などの躍進が続いている。欧州では脱ロシアエネルギーとカーボンニュートラルの両立に向けた政策転換が進み、SAF、クリーンメタノール、クリーン水素などの代替燃料開発が加速している。
国内石油コンビナートの国際競争力評価では、AHP法を用いて国内外25の主要コンビナートを比較分析した。2022年評価では米国ベイタウンがトップで、アジア地域ではインド・リライアンス、日本B、台湾麦寮が高評価となった。2026年評価でもベイタウンがトップを維持し、日本のコンビナートは競争力向上が見られるものの、アジアトップとの差拡大傾向にありスピード感のある競争力強化が必須である。
石精石化製品の需給バランス試算では、2026年度の全国TOP稼働量は3,090千BDと試算され、111千BDの余力が発生すると予測された。地域別では関東地域でTOP余力が0千BD、中部地域で101千BD、瀬戸内地域で10千BDの余力となり、地域インバランスは最小限の転送等で対応可能なレベルと推定された。重油需要の更なる減少に対応するため、VR留分の高分解への対応が最重要課題として挙げられている。
低炭素化コンビナート構築検討では、9地区の石油精製とエチレンセンターの2030年度CO2排出削減目標を設定し、ロードマップを策定した。2013年度比46%削減目標に対し、内需減による自然減1,313万トン、CN具体策による削減1,146万トンを見込むが、目標に対し476万トンの未達量が生じる。鹿島、川崎、周南は目標達成が可能である一方、千葉、水島、堺泉北は未達となり、これらの地区では自治体と企業の連携強化が必要である。