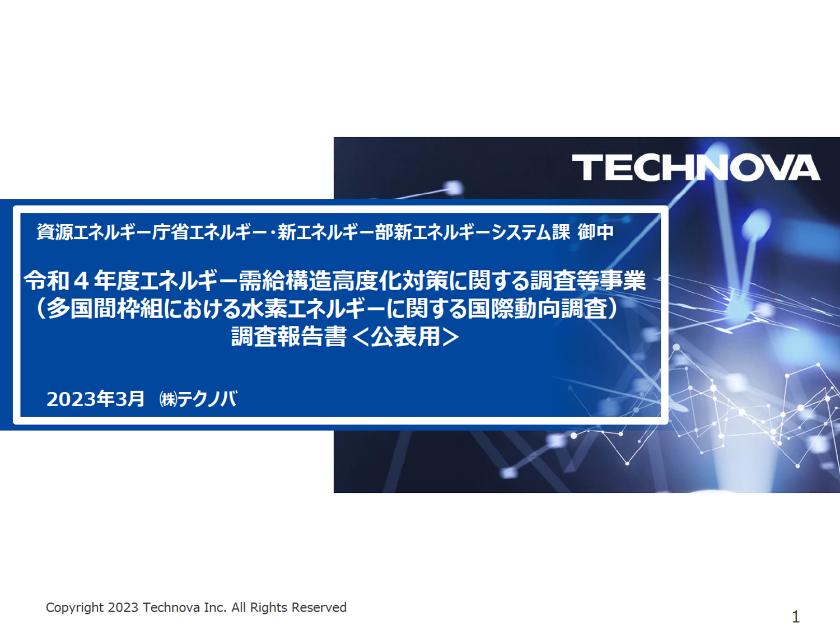令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(多国間枠組における水素エネルギーに関する国際動向調査)調査報告書<公表用>
報告書概要
この報告は、水素利活用促進に向けた多国間枠組みでの国際的な議論と取組について書かれた報告書である。
水素はカーボンニュートラル実現に必要不可欠な資源として、運輸・発電・産業など多様な分野の脱炭素化を可能とする新たなエネルギー源である。第6次エネルギー基本計画において水素は新たな資源として明確に位置づけられ、社会実装の加速が求められている。世界では日本が2017年に世界初の水素基本戦略を策定した後、EU、ドイツ、オランダ、豪州など多くの国が2020年以降急速に水素の国家戦略を策定している。
国際的には水素閣僚会議において日本が大規模需要創出や国際サプライチェーン構築を主導し、IEA、IPHE、CEM、Mission Innovation、QUADなどの多国間枠組みで水素の社会実装に向けた政策議論が活発化している。特にCO2フリーや低炭素といった定義づけ、水素製造時のCO2排出量評価に関する議論が重要となっている。
国際水素・燃料電池パートナーシップ(IPHE)は2003年に米国主導で設立され、日本は設立時からの加盟国として積極的に参加している。現在21カ国・地域が参加し、規制・基準・標準・安全に関するワーキンググループや教育・アウトリーチワーキンググループ、水素製造分析タスクフォースが活動している。
2022年のBreakthrough Agenda Reportでは、2030年までに再生可能エネルギー・低炭素で安価な水素を入手可能にする目標が示され、現在年間100万トン未満の再エネ・低炭素水素を年間1億4千万~1億5千500万トンまで拡大する必要があるとされている。そのため2023年から2030年にかけて水素製造能力を毎年倍増することが求められ、共通基準の策定、研究開発投資の継続、化石燃料由来水素の代替に向けたコミットメントが必要である。
水素認証分野では多くの国際機関が関心を示し、民間組織のHydrogen Councilも制度構築に取り組んでいる。多国間イニシアティブの中でIPHEは水素に特化した政府間組織として一定の存在力と影響力を有している。