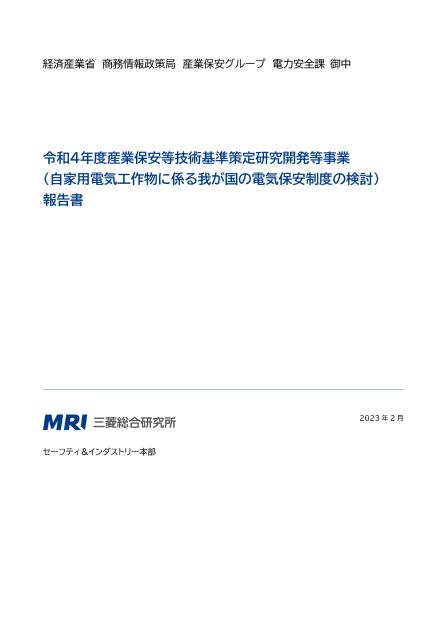令和4年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業(自家用電気工作物に係る我が国の電気保安制度の検討)報告書
報告書概要
この報告は、自家用電気工作物に係る我が国の電気保安制度について書かれた報告書である。経済産業省が令和4年度に実施した研究開発事業として、電気保安制度の現状分析と今後のあり方を検討したものである。
報告書では、電気事業法に基づく自家用電気工作物の保安規制について、その保護法益と基本的考え方を整理している。自家用電気工作物とは600Vを超える電圧で受電する設備や、50kW以上の太陽電池発電設備、20kW以上の風力発電設備などを指し、公共の安全確保のため電気主任技術者の選任や保安規程の作成が義務付けられている。
国内における現行制度の調査では、保安規制に関わるステークホルダーの整理を行い、各主体が担う役割・責任・利益について分析した。特に電気主任技術者制度に係る規制手段とその変遷を詳細に検討し、主任技術者不選任承認制度や外部委託承認制度の設備範囲の変化を追跡している。また、設備の経過年数と停電事故との関係を調査し、メーカー推奨更新年数に至らない機器では不具合が発生しにくいことを確認した。
海外調査では、米国、英国、仏国、独国、韓国を対象に電気保安制度を比較分析した。諸外国では国家資格者による保安管理ではなく、民間専門資格者による設備設計や行政機関による竣工検査により安全を確保する国があることを明らかにした。各国の保安管理規制に関わるステークホルダー関係図を整理し、停電等のトラブルに対する社会的受容性についても事例ベースで調査を実施した。
検討会では、学識経験者と有識者による計3回の議論を通じて、4つの重点項目について検討を行った。外部委託承認制度における月次・年次点検頻度の合理化については、独立行政法人製品評価技術基盤機構におけるスマート保安技術の評価により点検頻度の柔軟化を進める方向性を確認した。設備規模の規定合理化では、50kV未満で系統連系する10MWまでの太陽電池発電設備について第3種電気主任技術者の選任を認めることが合理的であるとの結論に達した。
保安管理責任者の早期現場駆付けである2時間ルールの合理化については、火災事故対応可能な1次対応者の設置、設備面での対策、送配電事業者との事前協議等の要件設定により緩和する方向性を確認した。これらの検討結果は、電気保安人材不足や再エネ発電設備増大、遠隔監視技術進展などの環境変化に対応した規制体系変革の基礎となるものである。