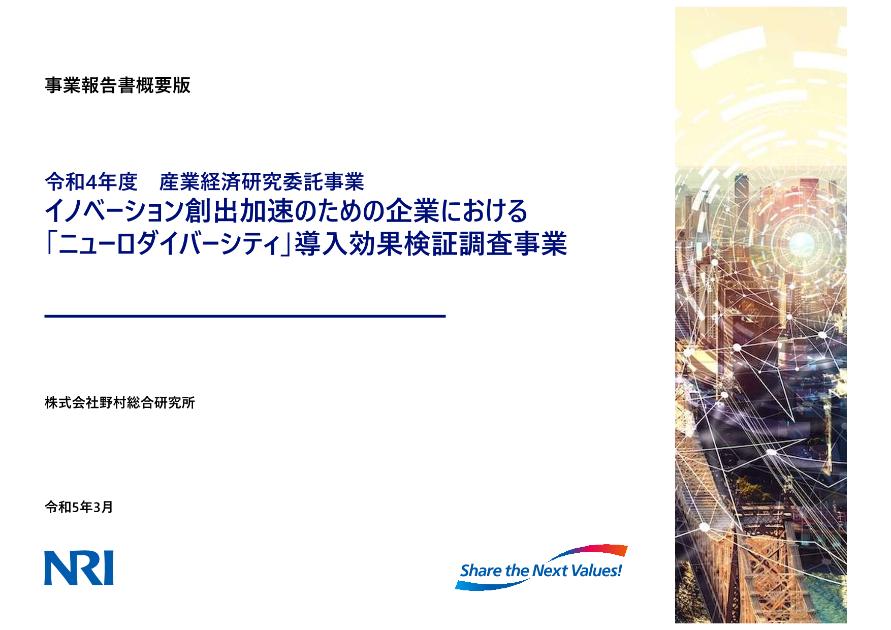令和4年度産業経済研究委託事業(イノベーション創出加速のための企業における「ニューロダイバーシティ」導入効果検証調査事業)事業報告書-概要版-
報告書概要
この報告は、企業におけるニューロダイバーシティの導入効果について検証した調査報告書である。ニューロダイバーシティとは、発達障害に関する研究や社会運動から生まれたダイバーシティの概念であり、脳や神経に由来する個人レベルでの様々な特性の違いを多様性として捉え、相互に尊重し、社会の中で活かそうとする考え方である。特にデジタル分野において高い親和性があるとされ、国内外で注目が集まっている。
海外では既にSAP、マイクロソフト、IBM、Google、JPモルガン・チェースなど多くの企業が発達障害のある人材を積極的に雇用しており、Harvard Business ReviewやReuters、The Wall Street Journalなどの主要メディアでも取り上げられている。これらの特性を持つ人材は特定の能力が非常に優れており、生産性、品質、革新性の向上など、企業に多種多様な恩恵をもたらし始めている。
企業がニューロダイバーシティに取り組む意義として、人材獲得競争の優位性、生産性の向上・イノベーションへの貢献、社会的責任の三つが挙げられる。発達障害のある方の中には、特性によりコミュニケーションに不得手を抱える方もおり、面接中心の採用方法では強みや能力が企業に伝わりにくいため、これまで見出せなかったり採用から漏れてしまっていた能力ある人材の採用に成功する企業が登場している。
令和3年度の研究では、ニューロダイバーシティ取組み企業で実践されている取組みが、チームの心理的安全性などを高め、イノベーション・生産性向上に繋がる可能性が示された。令和4年度には、水ing株式会社、ソフトバンク株式会社、日揮パラレルテクノロジーズ株式会社の3社で実証研究を実施し、当事者の新規受入れや定期的なコミュニケーションツール活用、個人ごとのキャリア設計、心理的安全性を高めるリーダー教育などの方法論を試行的に実践した。
実証研究の結果、人材活用可能性の拡大と組織力の強化という二つの効果が確認された。具体的には、当事者の職域拡大、人手不足の解消、コミュニケーションの活発化、業務の再整理、多様性を受容し認め合う文化の醸成などが見られた。これらの効果は、ニューロダイバーシティの取組み意義である人材獲得競争の優位性やイノベーション・生産性への貢献に繋がる可能性がある。