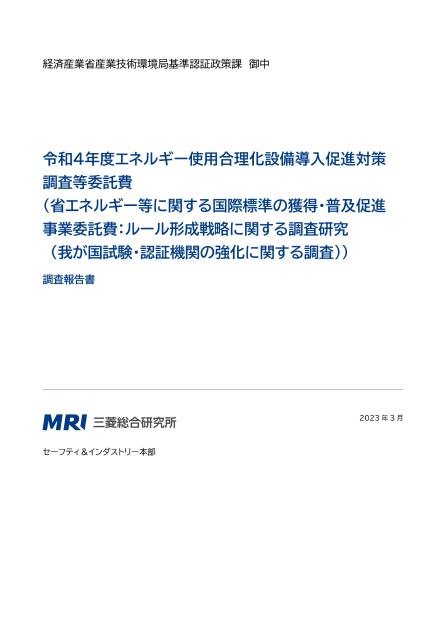令和4年度エネルギー使用合理化設備導入促進対策調査等委託費(省エネルギー等に関する国際標準の獲得・普及促進事業委託費:ルール形成戦略に関する調査研究(我が国試験・認証機関の強化に関する調査))調査報告書
報告書概要
この報告は、日本の試験・認証機関の強化策について検討した調査報告書である。
近年、各国政府や企業は自国に有利な規格・標準やルール形成を戦略的に推進しており、海外の巨大認証機関はキープレーヤーとして規格作成から認証実施まで一貫した体制でルール形成を有利に進めている。一方、日本は歴史的背景から小規模認証機関が多く、個々の機関ではユーザー企業の要求を全てカバーできない状況にある。標準化の対象分野はモノからエネルギー、環境、社会システム等の領域横断的・分野融合的なものへと拡大し、研究開発初期段階からの制度構築や標準化・認証スキーム構築の重要性が増大している。
調査では東京証券取引所上場の製造業企業を対象としたアンケート調査を実施し、日本企業による認証機関利用状況を分析した。その結果、製品認証における認証機関選定では、技術力や対応の迅速性、コストが重視される傾向が明らかになった。日本の認証機関は満足度は高いものの、外国機関と比較してコスト面での課題が存在することが判明した。
主要な試験・認証機関の調査では、日本品質保証機構、電気安全環境研究所等の国内機関と、TÜV SÜD、SGS、UL等のグローバル機関の事業内容や体制を比較分析した。グローバル認証機関は認証機能に加えてアドバイザリー機能やトレーニング機能を有し、顧客から新しい認証ニーズを汲み取って新たな認証スキーム創出に繋げている。これらの機関は市場創出の共同体であるコミッティに積極的に参画し、市場ニーズや技術シーズを特定して競争力向上を推進している。
領域横断的・分野融合的な規格認証への対応として、サーキュラーエコノミーやSDGs等の分野での包括的サービス提供によるビジネス拡大が重要である。日本の認証機関においても新市場への参入に向けた価値創造プロセスの明文化や多様なサービス提供体制の整備が必要となる。
R&D-製品化-規格化-認証までの一気通貫体制構築に向けては、市場ニーズ特定のためのコミッティへの積極的参画、国立研究機関や国際標準化機関との密な連携、規格・認証スキームの信頼担保と価値向上促進の取組みが必要である。認証機関が発行する認証が市場への影響力を持つためには認証マークの認知度と信頼性確保が重要であり、セミナーやシンポジウム等の啓発活動による認知度向上が求められる。