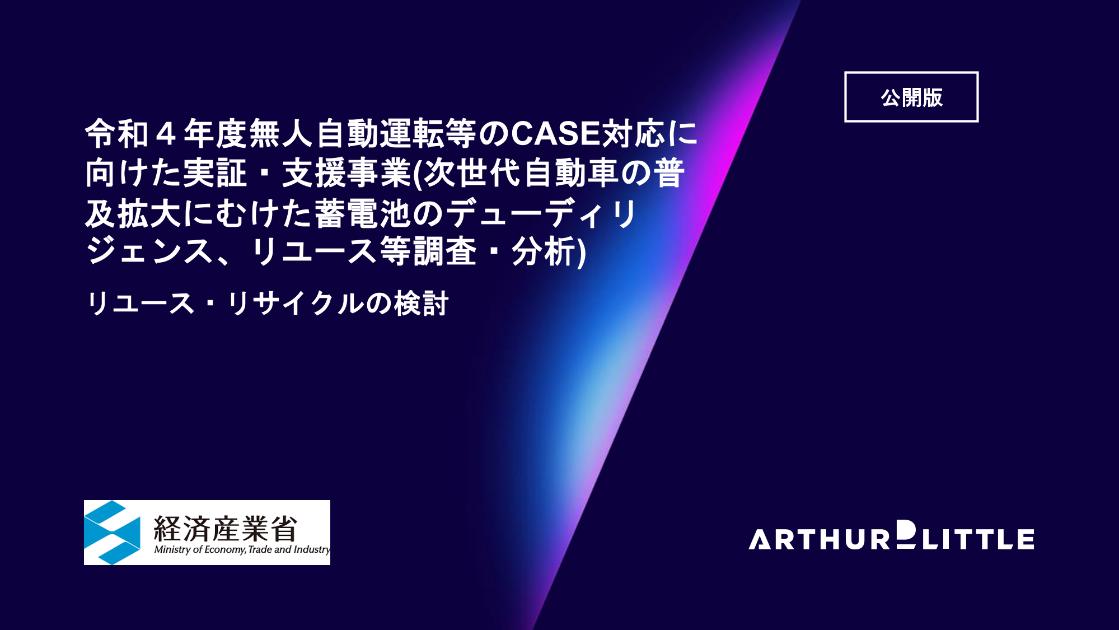令和4年度無人自動運転等のCASE対応に向けた実証・支援事業(次世代自動車の普及拡大にむけた蓄電池のデューディリジェンス、リユース等調査・分析) リュース・リサイクルの検討
報告書概要
この報告は、令和4年度に実施された蓄電池のデューディリジェンス(DD)に関する試行事業について書かれた報告書である。経済産業省が実施した次世代自動車の普及拡大に向けた蓄電池のサステナビリティ確保を目的とした実証・支援事業の成果をまとめている。
試行事業では、OECDデューディリジェンスガイドラインを参考として、蓄電池のサプライチェーンにおける責任ある調達を実現するためのDD帳票を開発した。対象鉱物はコバルト、リチウム、ニッケル、グラファイトの4種類であり、環境リスクと人権リスクの計9つのリスク項目を設定している。環境リスクには大気汚染、水質汚染、土壌汚染、生物多様性への影響が含まれ、人権リスクには健康被害、地域コミュニティへの影響、労働衛生・安全、強制労働、児童労働が含まれている。
DD帳票は電池メーカー、サプライヤー、精錬・製錬業者向けの質問票と参考資料から構成され、日英両言語で計10シートにより構成されている。試行事業の実施体制では、電池メーカーから上流のサプライヤーへと順次帳票記入を依頼し、精錬・製錬業者まで情報収集を行う回収スキームを採用した。令和4年8月から令和5年2月にかけて実施された試行事業では、延べ120社以上から回答を収集することに成功している。
実施結果として、4鉱物すべてについて精錬・製錬業者まで追跡可能であることが実証され、国内外の事業者からの回答収集も実現できた。現地調査の実施率は全体で4~5割程度であり、上流企業ほど実施率が高い傾向が確認されている。また、リユース・リサイクルの検討においては、中古電池の残価評価技術や異種電池の接続制御技術が重要であることが示されており、実際にトヨタ・JERAによる神戸関西圏での実証実験や大阪ガスによる系統用蓄電池への再利用事業化の取り組みが紹介されている。本試行事業により、蓄電池サプライチェーンの透明性向上とサステナビリティ確保に向けた実効性のあるDD体制構築の基盤が整備されたといえる。