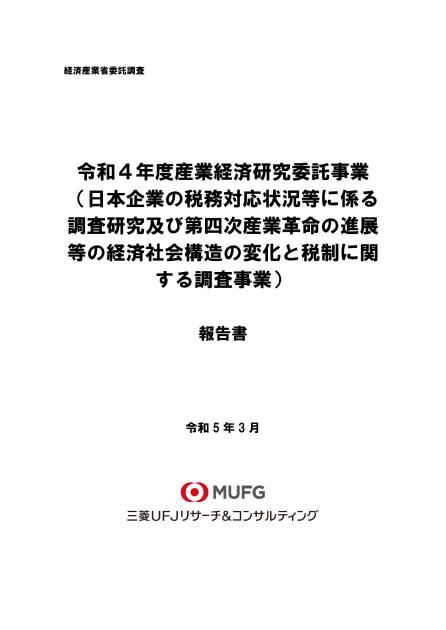令和4年度産業経済研究委託事業(日本企業の税務対応状況等に係る調査研究及び第四次産業革命の進展等の経済社会構造の変化と税制に関する調査事業)報告書
報告書概要
この報告は、令和4年度に経済産業省が実施した日本企業の税務対応状況と第四次産業革命に伴う経済社会構造の変化が税制に与える影響について調査研究した報告書である。本調査は、我が国の産業競争力向上と経済の好循環実現に向けて、成長志向の税制改正の効果を定量的に把握し、マクロ経済政策の在り方を検討することを目的としている。
第一部では、資本金1億円超の企業17,756社を対象としたアンケート調査により、4,094社からの回答を得て企業の税負担実態を分析した。企業規模を中堅企業(資本金1億円超10億円以下)と大企業(資本金10億円超)に区分し、産業分類では卸売業、不動産業、サービス業の順で回答企業の割合が高かった。納税方式については76.8%が単独納税、連結納税は23.2%であり、企業規模が大きいほど連結納税の比率が高くなる傾向が確認された。企業の税負担率は、法人税額、法人住民税額、法人事業税額の合計を税引前当期純利益で除した指標として算定し、税制優遇措置の影響を含めた実態を把握した。
第二部では、マクロ経済政策について、2010年代以降の世界経済の特徴である長期停滞論を中心に調査分析を行った。長期停滞論は、先進国において自然利子率の低下により名目金利がゼロ制約に直面し、伝統的な金融政策の効果が限定的となる状況を説明する理論である。この状況下では、フォワード・ガイダンスや量的緩和、マイナス金利政策などの非伝統的金融政策が各国中央銀行により実施されている。また、人口動態や安全保障、脱炭素化の推進等の環境変化により、今後の財政支出は大幅に増加することが予想され、EU諸国では政府支出がGDP比で2~3%程度増加する見込みである。高齢化社会の進展は自然利子率に対して複雑な影響を与え、貯蓄率上昇による金利低下説と労働者・年金受給者比率低下による金利上昇説が並存している。近年のインフレ率上昇を受けて、各国中央銀行は政策金利引き上げ等の金融引き締め策を実施しているが、インフレ抑制には相当なコストを要し、失業率の上昇を伴うことが指摘されている。