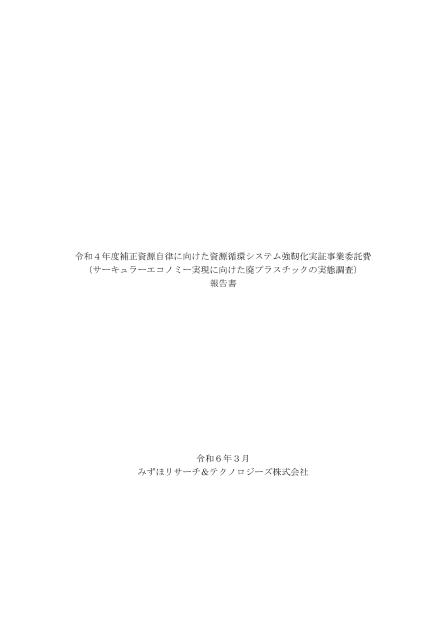令和4年度補正資源自律に向けた資源循環システム強靭化実証事業委託費(サーキュラーエコノミー実現に向けた廃プラスチックの実態調査) 報告書
報告書概要
この報告は、サーキュラーエコノミー実現に向けた廃プラスチックの実態調査について書かれた報告書である。世界的な資源制約や環境問題を背景に、線形経済から循環経済への移行が進む中、我が国では製品廃棄時の廃プラスチックの約6割がサーマルリカバリーされている状況にある。この中でマテリアルリサイクル適性の高い製品があると考えられることから、プラスチックの大宗を占めるポリエチレンとポリプロピレンを対象に、国内における排出実態の調査が実施された。
調査においては、廃棄物に関する統計等をベースとした推計とプラスチック循環利用協会のマテリアルフローをベースとした推計という二つの方法により、廃プラスチックの排出実態把握が行われた。一般廃棄物では環境省の容器包装廃棄物実態調査データを活用し、容器包装プラスチック類が79.7%、容器包装以外のプラスチック類が20.3%を占めることが明らかとなった。産業廃棄物についても同様の手法で分析が実施され、全国及び四大都市圏における廃プラスチックの樹脂種別・処理方法別の量が推計された。
ヒアリング調査では、多くの事業者において定量的な廃プラスチック排出実態の把握がなされていない状況が確認された。製造端材のようなマテリアルリサイクルに適した廃プラスチックは既にリサイクルされており、多くの企業により廃プラスチックが奪い合いの状況にあることが判明した。また、排出段階で分別されていない産業廃棄物や実態把握が進んでいない事業系一般廃棄物に混在する廃プラスチックがマテリアルリサイクル促進の検討余地があると指摘された。
マテリアルフローや推計量の精緻化に向けては、製品種類別の排出実態、自治体の属性別排出量、業種別・樹脂種類別の排出状況と処理方法等の実態データが不足しており、これらの把握が重要課題として整理された。短期的な実態把握が困難な項目として、有価での取引実態やデータの不確かさを補正した排出実態等が挙げられている。
マテリアルリサイクル促進に向けた課題として、消費者における樹脂種類の判別困難性、市区町村の分別促進に係る人員確保問題、リサイクラーにおける高品質再生材確保の困難性、製造メーカーの再生材需要増加等が特定された。これらの課題解決には、環境配慮設計の促進、適切な周知啓発、関連主体の協働による需要創出、技術開発の推進が必要とされる。特に情報基盤の整備により、再生材の需要・供給情報の見える化とトレーサビリティ確保が重要な共通課題として提示されている。