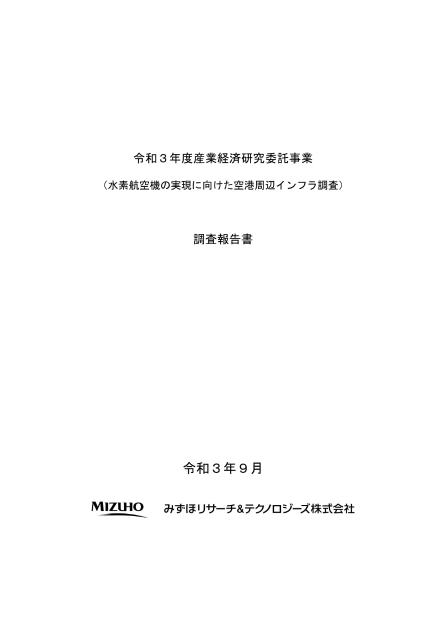令和3年度産業経済研究委託事業(水素航空機の実現に向けた空港周辺インフラ調査)調査報告書
報告書概要
この報告は、水素航空機の実現に向けた空港周辺インフラについて書かれた報告書である。国際民間航空機関(ICAO)が2020年以降の国際航空におけるCO₂排出量増加抑制目標を採択する中、航空機産業の低炭素化要求が強まっており、革新的技術として水素航空機の研究開発が世界的に加速されている。エアバス社は2020年9月に水素を燃料としたゼロ・エミッション航空機の3つのコンセプトを提唱し、2035年までの実現を目指している。
欧州のClean Sky 2によると、水素航空機の開発は小型機から開始され、2030年までに航続距離500km程度、2035年までに2,000km程度の航空機導入が見込まれている。導入初期には地方空港への小型水素航空機導入、将来的には大都市空港や大型航空機への展開が想定されている。初期段階では液化水素貯蔵タンクと運搬車両が主要インフラとなり、本格導入時には水素対応ハイドラントシステムの構築が必要となる。
空港周辺インフラとして、貯油タンク、ポンプ、地下ピット、ハイドラントバルブ、給油車両が極低温液化水素への対応を求められる。年間5,000トン程度の燃料量が想定され、3日分の液化水素90トン保管には約100m²のスペースが必要である。液化水素の充填速度は従来のジェット燃料より遅く、ターンアラウンドタイムへの影響が懸念されるため、技術開発が必要である。
実現に向けた主要課題として、十分な水素燃料確保とコスト、輸送形態の決定、ハイドラントシステムの仕様整理、貯蔵・液化設備の設置要件、充填速度向上、安全性確保、法整備、人材育成が挙げられる。今後は具体的空港を想定した設備コスト検討、充填時間短縮技術開発、空港内車両の課題検討、燃料製造・輸送方法比較、CO₂評価、国際標準化対応が重要な検討項目である。