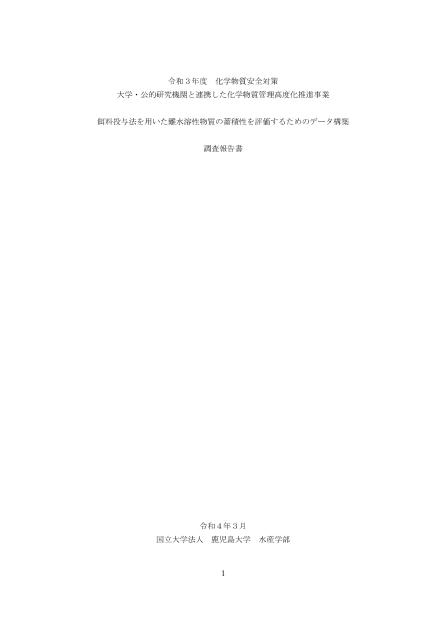令和3年度化学物質安全対策「大学・公的研究機関と連携した化学物質管理高度化推進事業(餌料投与法を用いた難水溶性物質の蓄積性を評価するためのデータ構築)」調査報告書
報告書概要
この報告は、難水溶性物質の経口蓄積性を評価するための餌料投与法による試験データの構築について書かれた報告書である。鹿児島大学水産学部の研究チームが令和3年度に実施した化学物質安全対策事業の調査結果をまとめており、化審法における化学物質蓄積性評価の科学的基盤構築を目的としている。
研究では、logKow5以上の難水溶性物質を対象として、多環芳香族炭化水素類(PAHs)、農薬類、ビフェニル類の三つのグループに分類し、それぞれの物質群を混合した餌をコイに28日間経口投与する暴露試験を実施した。PAHs類には石油や燃焼由来のピレン、ベンゾ(a)アントラセン、クリセン、ベンゾ(a)ピレンなど6物質、農薬類にはPRTR対象物質であるベンチオカーブ、クロルピリホス、オキサジアゾンなど6物質、ビフェニル類にはo-テルフェニル、m-テルフェニル、p-テルフェニル、トリフェニルメタンなど5物質を選定した。実験装置は流水式水槽システムを構築し、工業用液体充填機を用いて安定した水流速を維持することで、残餌や糞による水質汚染を防止した。
分析の結果、選定した物質のうち経口蓄積性を示す生物蓄積係数(BMF)が0.007を超える物質は、ビフェニル類高濃度暴露区のo-テルフェニルとトリフェニルメタンのみであった。PAHs類と農薬類については、いずれもBMFが低い値を示し、経口蓄積性は認められなかった。この結果は、POPs以外の既存物質で環境中から検出される物質群では、0.007の基準値を超える物質は多くないものの、ある程度存在することを示している。また、化学物質のlogKowの増加に伴い立体構造が大きくなる傾向があり、腸管からの吸収が減少することから、より小さなlogKowを持つ化学物質群にBMFが高い物質が存在する可能性も示唆された。さらに、魚種間によるBMFの差が大きい可能性も指摘され、化審法での経口濃縮試験適用と現行BMF設定値の正当性を検討する上で、種間差の検討も重要であると結論づけている。