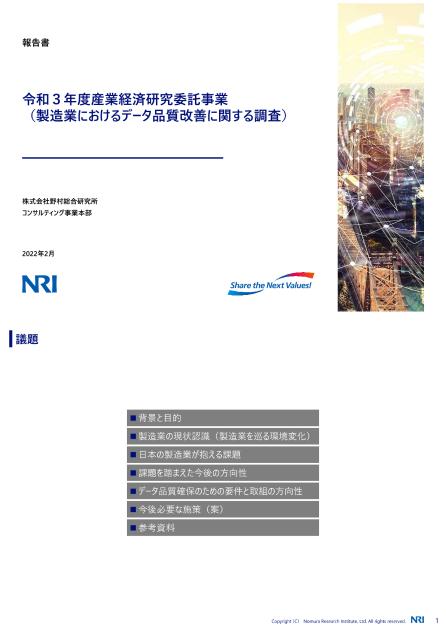令和3年度産業経済研究委託事業(製造業におけるデータ品質改善に関する調査)報告書
報告書概要
この報告は、製造業におけるデータ品質改善に関する調査について書かれた報告書である。
情報通信技術の発達により、企業活動で生成されるデータが指数関数的に増大している中、製造業がリアルデータをサイバー空間に集約し、AI等の新技術を活用してデジタルツインなどの付加価値創出を図る動きが活発化している状況を背景としている。しかし、日本の製造業は現場主義と改善文化による成功体験から現状システムに過度に最適化された「経路依存性の罠」に陥っており、組織間連携が困難な問題を抱えている。これを克服するため、システム中心からデータ中心の設計思想への転換が求められており、そのための課題と取組内容の明確化が必要となっている。
データ流通による具体的な価値として、多様な企業のマシン稼働データをAIに学習させた予兆保全の予測精度向上や、加工データの活用による最適加工条件の発見などが期待されているが、これらの効果を得るためにはデータ品質の担保が必須となる。データ品質の国際標準であるISO8000では、データ品質を「目的適合性」として定義し、構文的品質、意味的品質、実用的品質の三つのカテゴリで評価する枠組みを提供している。
製造業が直面する環境変化として、VUCAな経営環境における不確実性の増大、ユーザニーズの多様化に対応するマスカスタマイゼーション、サプライチェーンの脆弱性、人手不足と熟練技能の散逸、カーボンニュートラルへの対応等が挙げられる。これらの課題に対応するためには、見込み生産と受注生産のハイブリッド化、在庫の可視化による最適な在庫管理、設計と生産の分断解消が重要である。
データ品質改善の実現に向けては、①データ品質基準の策定、②データ品質認証制度の構築、③データ流通指標・格付制度の確立という三本柱による包括的なアプローチが提案されている。また、需要表現コンソーシアムの設立により、ユーザとベンダが協調してデータ流通要件を明確化し、第三者認証機関による評価体制を整備することで、製造業のデータ駆動型経営への転換を支援する施策が必要である。