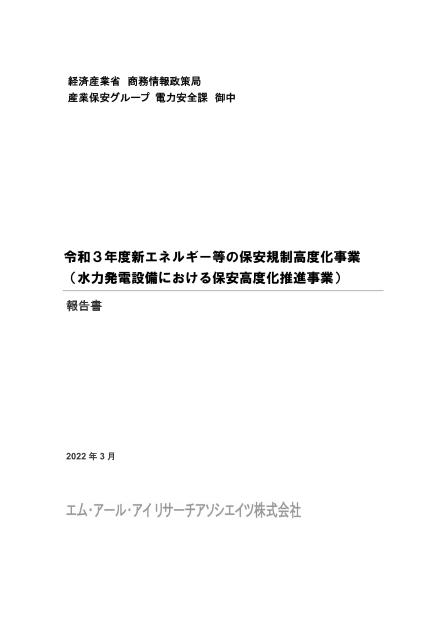令和3年度新エネルギー等の保安規制高度化事業(水力発電設備における保安高度化推進事業)報告書
報告書概要
この報告は、水力発電設備における保安管理業務のスマート化技術導入について書かれた報告書である。経済産業省による令和3年度新エネルギー等の保安規制高度化事業として実施され、水力発電設備のICT等を活用した遠隔保守(スマート保安)の導入・運用に関するガイドライン策定を目的としている。
背景として、FIT制度開始以来再生可能エネルギーによる発電が増加する一方、水力発電は安定的な電力供給が可能な調整力として期待されているものの、公営等の中小水力発電事業者では設備の経年化と技術的ノウハウを持つ職員の定年退職により保守管理体制の弱体化が懸念されている。このため、センサーやデータ活用等を通じた先進的な保守管理手法の導入が求められている状況である。
事業内容は6つの柱から構成される。令和2年度スマート保安技術実証事業費補助金の発電事業者への実証事業内容調査では、一次補正予算で長野県企業局、山梨県企業局、宮崎県企業局、中国電力の4事業者5事業、三次補正予算で長野県企業局、徳島県企業局、神奈川県企業庁の3事業者3事業について調査した。これらは温度・振動センサーによる機器情報のデータ化、インターネット回線を利用したWebカメラによる遠隔監視・制御、ネットワークカメラによる発電所監視強化、特定小電力無線通信による雨量データ伝送、IoT装置によるセンシング値のデジタル化とクラウドサーバとのデータ通信システム構築等の実証を行った。
スマート保安技術の先行導入事例調査では、国内事例として関西電力と北海道電力の取組を調査した。関西電力では振動監視システムや画像解析による設備状態監視技術の開発を行い、北海道電力では保守支援装置の導入により遠隔監視効果を踏まえた巡視頻度の延伸、定期点検頻度の延伸、オーバーホール周期の延伸等の検討を実施している。
他分野のIoT等導入ガイドライン等調査では、電気保安分野、高圧ガス分野、上下水道分野における取組を調査し、特に上下水道分野では水力発電事業と共通する課題背景を有し、遠隔監視システム、点検データのデジタル化、劣化診断予測等のスマート化に取り組んでいることが判明した。期待される効果として保守作業の時間・負荷軽減、施設運用・維持費用の削減、保守品質の向上等が挙げられ、その評価指標も水力発電と類似している。
これらの調査結果を踏まえ、「水力発電設備における保安管理業務のスマート化技術導入ガイドライン」を策定した。昨年度の導入フェーズガイドラインに続き、今年度は運用フェーズの内容を追記し、スマート化技術導入効果の算定指標・方法、継続的な維持・管理、人材育成等の留意事項、実証事業での取組事例、先行事例等を盛り込んだ。また、有識者による検討会を3回開催し、ガイドライン策定に向けた調査・検討内容の議論を実施した。
公営水力等のスマート化技術導入における保安規程の検討では、巡視点検頻度の見直し事例や課題等を整理した。遠隔監視により現場でのメーター数値確認は代替可能であり、巡視・点検頻度の削減やチェック項目の見直しが可能となる一方、主任技術者のチェックエビデンス準備や機器故障時の対応等が課題として挙げられた。本事業により、水力発電事業者がスマート保安を導入・運用する際の参考となるガイドラインが整備され、今後の保安業務の効率化と品質向上が期待される。