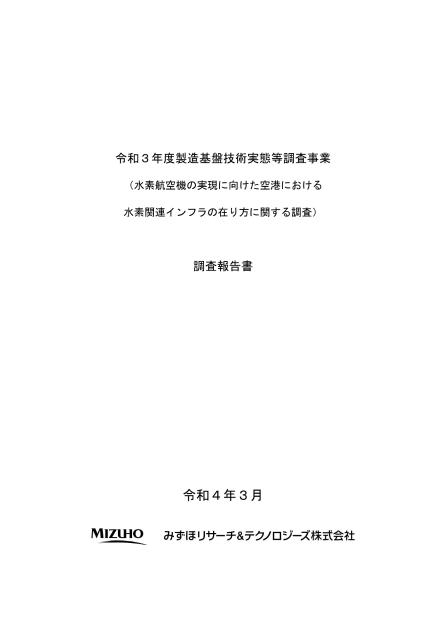令和3年度製造基盤技術実態等調査事業(水素航空機の実現に向けた空港における水素関連インフラの在り方に関する調査)調査報告書
報告書概要
この報告は、水素航空機の実現に向けた空港における水素関連インフラの在り方について書かれた報告書である。
国際民間航空機関が2020年以降CO₂排出量を増加させないとの目標を採択し、航空機産業においても低炭素化の要求が強まる中、革新的技術として水素航空機の研究開発が世界的に加速している。エアバス社が2035年に水素航空機を市場投入すると発表し、国内でも川崎重工業がNEDOのグリーンイノベーション基金事業として水素航空機向けコア技術開発を実施している。
報告書では水素航空機導入に必要な空港周辺インフラについて、立地と規模の観点から空港を類型化し、コスト試算を実施した。導入シナリオとして2035年頃に定員100人以下の小型ターボプロップ機から導入開始、2040年頃に定員200人程度のターボファン機の導入を想定している。コスト試算は導入初期と導入中期の3つのシナリオで行われ、水素燃料のコストと液化水素貯蔵タンクに関わるコストが大半を占めることが判明した。
空港の類型化では燃料受け入れ方法に影響する立地と設備規模に影響する空港規模を組み合わせた指標を用い、4つの類型化空港を選定してコスト試算を実施した。導入初期に最低限のインフラを整備する場合、水素輸送の容易さや既存貯蔵施設の利用可能性が重要な要因となる。設備規模の検討では、将来の水素航空機数増加を見越して初期段階から設備を設置する方が旅客・kmあたりのコストがわずかに安価になる結果を得た。
課題として液化水素ポンプをはじめとした水素インフラの技術開発、空港におけるジェット燃料との併用検討、法令整備等が必要である。現時点では液化水素用レフューラーが市場製品として存在せず、新規開発が必要な状況である。また用地確保や既存インフラとの併用、安全な離隔距離の検討も重要な課題である。水素航空機は運航時にCO₂を排出しない利点があり、将来の強い環境規制下では注目される可能性がある。航空業界ではSAFの導入検討も進められており、水素航空機とSAFのすみ分けによる航空分野でのCO₂排出量削減が期待される。