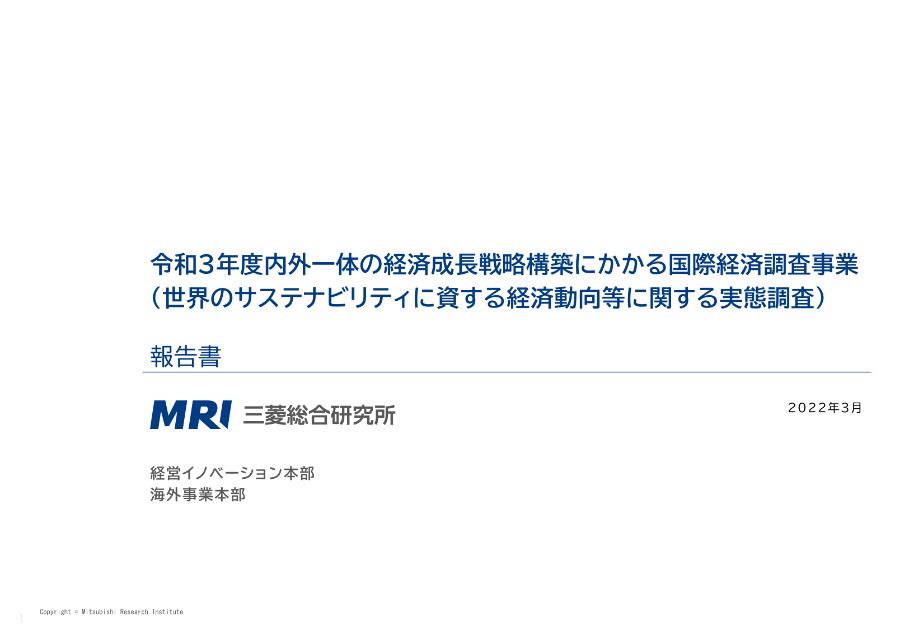令和3年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(世界のサステナビリティに資する経済動向等に関する実態調査)報告書
報告書概要
この報告は、世界のサステナビリティや持続可能な開発目標(SDGs)による国際経済システムへの影響とその実態について書かれた報告書である。
報告書では、1984年のブルントラント委員会から始まる持続可能な開発の概念の歴史的発展を詳細に追跡している。1992年の地球サミットにおける「持続可能な開発」の提唱、2000年のミレニアム開発目標(MDGs)の制定、そして2015年のSDGs採択に至る一連の国際的な取り組みが体系的に整理されている。特に日本においては、経団連による「1%クラブ」設立(1990年)、経団連地球憲章制定(1991年)、CSR元年とされる2003年の企業のCSR部門設立、2016年のSDGs推進本部発足など、企業と政府の持続可能性への取り組み進化が詳述されている。
環境分野では、気候変動対応として1994年の国連気候変動枠組条約発効から2015年のパリ協定採択、2021年のグラスゴー気候合意に至る国際的な枠組み構築過程が分析されている。生物多様性保全やサーキュラーエコノミーの発展についても、欧州のサーキュラーエコノミーパッケージや日本の循環型社会形成推進法などの政策展開が検証されている。
金融分野においては、ESG投資の拡大、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の発足、企業のサステナビリティ報告書の普及など、非財務情報開示の重要性増大が論じられている。また、2008年のリーマンショック後に欧米企業がサステナビリティ経営の重要性を認識し、長期的視点からのリスク回避戦略として位置づけるようになった変化も示されている。
さらに、地域別のSDGsの進捗状況として、欧州、米国、中国、インド、日本の現状評価が数値データとともに提示されており、各国・地域の特徴的な取り組みと課題が明確化されている。企業の取り組み事例では、ユニリーバやマイクロソフトなどの先進企業による具体的なサステナビリティ戦略の実装状況が詳細に分析されている。