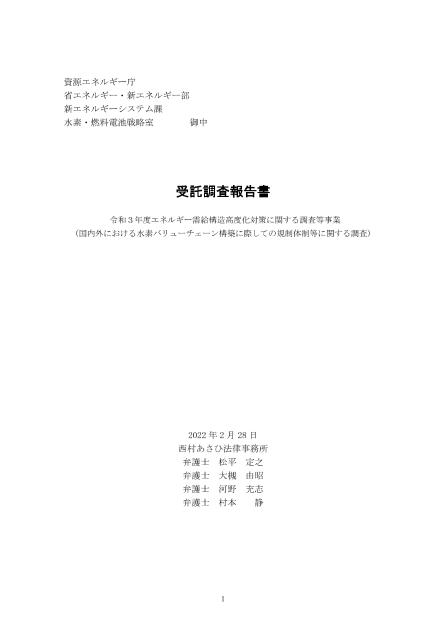令和3年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(国内外における水素バリューチェーン構築に際しての規制体制等に関する調査)調査報告書
報告書概要
この報告は、国内外における水素バリューチェーン構築に際しての規制体制等について調査した報告書である。
導管を通じた水素の供給については、ガス事業法と高圧ガス保安法のいずれが適用されるかが必ずしも明確でないという問題がある。ガス事業法における「一般の需要」の概念は不特定多数への供給を意味するが、その判断基準が社会通念に委ねられているため、水素供給事業者にとって適用法令の確定が困難な場合がある。特に、特定の産業需要家への供給が多い水素事業では、「一般の需要」に該当するか否かの判断が重要な論点となる。
水素製造に関しては、水電解装置が電気事業法の対象となる可能性があり、また発生する水素の配管等については高圧ガス保安法が適用される。水素の発電利用においては、発電設備への供給が電気事業法の適用対象となり、設備の運営・管理権の帰属によって責任分界点が決定される。
水素の受入・貯蔵については、液化水素貯蔵設備の容量や用途によってガス事業法、電気事業法、高圧ガス保安法のいずれが適用されるかが決まる。特に、貯蔵設備の容量が二十万キロリットル以上でガス事業用導管と接続している場合はガス製造事業に該当する。
これらの規制体制において、同種の設備であっても供給対象や容量等の微妙な違いによって適用法令が変動することがあり、事業者にとって確定的判断が困難な状況が生じている。各法令に基づく技術基準や保安規程、主任技術者の選任等の要求事項も異なるため、水素事業の実施において法的不確実性が課題となっている。