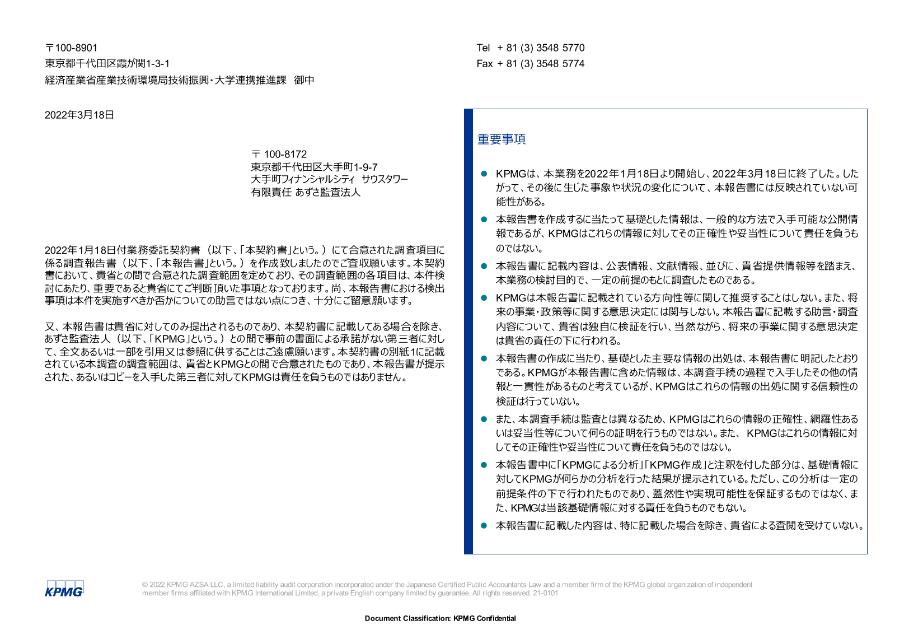令和3年度戦略的基盤技術高度化・連携支援事業(企業の新しい研究開発形態に対する会計処理に関する実態調査)に係る調査報告書
報告書概要
この報告は、企業の新しい研究開発形態に対する会計処理に関する実態調査について書かれた報告書である。
デジタル革命等の進展により、企業の研究開発活動は自社内に閉じた従来の形態から顧客との共創による研究開発へと変化している。さらに、自然科学分野のみならず人文科学、社会科学分野を総合的に組み合わせた新たな領域の深耕が試みられている。現行の企業会計基準における研究開発の定義は製造業の研究所等における集中開発を前提としており、現在の研究開発活動の新潮流におけるニーズを満たすものとは言い難い状況となっている。
本調査は、企業の新しい研究開発活動実態を具体的に把握し、現行の研究開発税制における会計処理上の課題を調査したものである。2020年度の我が国の科学技術研究費は19兆円で、国内総生産に対する比率は3.59%であった。研究主体別では企業が14兆円と全体の70%を占めており、研究開発活動の大半が企業で行われている。費目別では人件費の割合が大きく、全体の40%を占めている。
調査では、企業の研究開発形態の変化を顧客共創型、多種領域複合型、専門知見活用型、実証データ活用・転用型と分類したうえで、ヒアリング調査を通じてその実態を調査した。その結果、各分類において研究開発としての要素を備えながらも、その活動を切り分けて捕捉することが実務上困難であるため制度の恩恵を得られていない点や、従来の研究開発の定義との乖離を背景に研究開発として認識されにくい点が確認された。
特に、ソフトウェア開発におけるアジャイル型開発や、サービス開発、中小・ベンチャー企業における開発では、市場・顧客に近い領域での研究開発、通常業務との連続性が高い研究開発において、活動が研究開発としての性質を備えていても切り出して工数・費用等を捕捉するのは相応のコストを要する。また、クラウド型・サブスクリプション型で提供されるSaaSの開発、デザイン・UI/UX、人文・社会科学的知見を活用した開発における研究開発は、会計基準設定時には想定していない取引に関して多様な実務が生じており、研究開発の定義との乖離から研究開発と認識されない事例が多い。