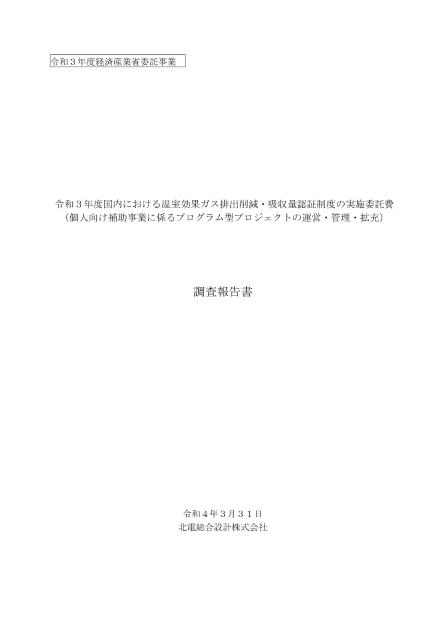令和3年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費(個人向け補助事業等に係るプログラム型プロジェクトの運営・管理・拡充)調査報告書
報告書概要
この報告は、令和3年度における国内温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度(J-クレジット制度)の個人向け補助事業に係るプログラム型プロジェクトの運営・管理・拡充について書かれた調査報告書である。
本事業は、経済産業省のJ-クレジット制度に従い、個人向け新エネ機器導入補助事業等から生じる各個人の排出削減による環境価値を取りまとめ、クレジット化することを目的としている。対象となるプログラム型排出削減プロジェクトは、グリーン・リンケージ倶楽部とJ-グリーン・リンケージ倶楽部の2つで構成され、太陽光発電、燃料電池、電気自動車の各分野において平成23年度から令和3年度までの補助事業を網羅している。認証申請期間は各倶楽部・設備種別により異なり、グリーン・リンケージ倶楽部では15ヶ月間、J-グリーン・リンケージ倶楽部では11ヶ月から23ヶ月間となっている。
サンプリング対象者の抽出及びモニタリング業務においては、J-クレジット制度のモニタリング・算定規定に基づき、層化無作為抽出法を用いて各倶楽部から必要サンプル数を算定した。母集団は各倶楽部の会員総数で、太陽光発電では約30万から36万人、燃料電池では約16万から22万人、電気自動車では約3万から5万人となっている。モニタリング依頼数は太陽光発電1000件、燃料電池700件(グリーン・リンケージ倶楽部のみ1200件)、電気自動車700件とし、郵送とホームページ入力により回収を行った。モニタリング項目は設備種別により定められ、太陽光発電では累積発電量と売電量、燃料電池では累積発電量と自家消費量、電気自動車では走行距離を写真撮影により収集した。
今後の新たな提案として、サイクルシェアリングによるCO2排出削減効果の評価手法の検討が示されている。従来の評価手法では、自動車からサイクルシェアリングへの転換率のみを考慮していたが、新しい評価手法では公共交通も含めた包括的な転換効果とトラック等による再配置作業に伴うCO2排出量を考慮した総合的な評価が提案されている。実現に向けては、GPS データ等のビッグデータと組み合わせた利用実態分析や、無線通信サービス会社からのモニタリングデータ提供による効率的なデータ収集方法が検討されている。来年度に向けた課題として、モニタリング依頼数の増加、依頼文書の簡素化、二重認証の確認プロセスの改善等が挙げられている。