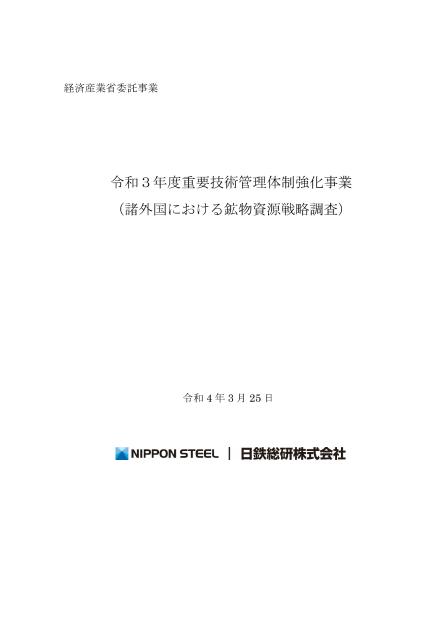令和3年度重要技術管理体制強化事業(諸外国における鉱物資源戦略調査)報告書
報告書概要
この報告は、令和3年度重要技術管理体制強化事業として実施された諸外国における鉱物資源戦略調査について書かれた報告書である。2015年のパリ協定以降、120以上の国と地域が2050年カーボンニュートラル目標を掲げており、次世代自動車や再生可能エネルギー関連設備の導入が急速に進められている。これらの技術には特定の国に資源が集中するレアアースやレアメタルが必要不可欠となっている。そのため各国は鉱物資源戦略の策定及び国外鉱山権益の確保、国内資源の探索・防衛、国家備蓄等の取組を強化している。日本は重要鉱物の大宗を輸入に依存しており、安定供給確保のためには他国の鉱物資源戦略と主要資源国の保護貿易主義の進捗を把握し、政策に反映する必要がある。本調査では、日本を含む米国、欧州、中国、インド、豪州における重要鉱物の選定基準と資源政策を比較分析している。米国は2018年に35鉱種を重要鉱物に指定し、2021年には50鉱種に拡大した。欧州は27の重要原材料を選定し、中国は10鉱種を戦略的鉱物として位置づけている。各国の探鉱費予算分析では、世界全体でバッテリーマテリアルへの投資が急増していることが確認された。銅、ニッケル、コバルト、リチウムについては、サプライチェーン概況から中国が海外鉱山権益の取得を積極的に進めており、特にアフリカやインドネシアでの権益確保が顕著である。生産コストカーブ分析では、中国資本の鉱山権益取得により生産量が増加傾向にあることが示された。環境負荷分析では、鉱山のGHG排出量と水使用量の関係を調査し、地域別、鉱石種別、品位別の比較を実施した。中国資本が権益を有する海外鉱山は環境負荷が比較的高い傾向にあることが判明した。その他の鉱種としてグラファイト、金、鉄鉱石、鉛、モリブデン等についても同様の分析を行った結果、中国による海外鉱山権益の取得が広範囲にわたって進んでいることが確認された。