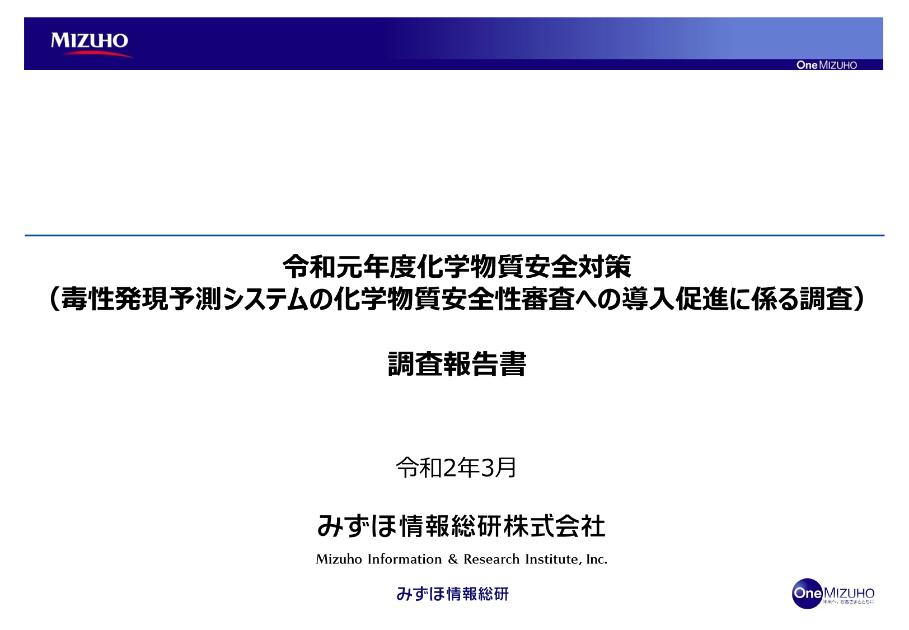令和元年度化学物質安全対策(毒性発現予測システムの化学物質安全性審査への導入促進に係る調査)調査報告書
報告書概要
この報告は、化学物質の安全性評価における毒性発現予測システムの行政利用促進について書かれた報告書である。日本では化審法に基づく化学物質の安全性審査において、従来はラット等を用いた動物試験による毒性評価が求められているが、これらの試験は多大な費用と時間を要するため事業者の大きな負担となっている。一方、欧州や米国では動物実験廃止の潮流もあり、コンピューター・シミュレーションによるインシリコ手法の活用が積極的に進められている。
我が国では「有害性評価支援システム統合プラットフォーム(HESS)」を開発したものの、予測精度の検証や活用実績が不十分であることから、現時点では法令上の安全性評価手法として十分な行政利用ができていない。そこで本調査では、欧州REACH規則や米国TSCAにおけるQSAR等の行政活用状況を調査し、国内での活用における課題を抽出した。
調査の結果、欧州では登録時にQSARの使用条件が規定され、ECHAによる評価が実施されているが、リードアクロスを用いた107件のコンプライアンスチェックでは受け入れられた件数が1~2件程度と低い状況である。主な却下理由として、物質の構造不定、正当性を立証する証拠不足、科学的妥当性の欠如等が挙げられている。また、EU-ToxRiskやTox21等の代替試験法開発プロジェクトが進行中であり、APCRA等の規制当局横断的プロジェクトでもQSAR活用が検討されている。
国内外の毒性試験情報については、REACH登録データを含む120物質以上を選定し、反復投与毒性試験データの収集・分析を実施した。ケミカルスペース分析により、類似構造を持つ物質の毒性データ収集がQSAR予測範囲の拡大に有効であることが示された。また、Cramer分類を用いてREACH化合物を3つのクラスに分類し、学習データ収集時の考慮事項として提示した。これらの調査結果を踏まえ、国内におけるインシリコ手法の行政利用促進に向けた課題整理と活用方策が検討された。