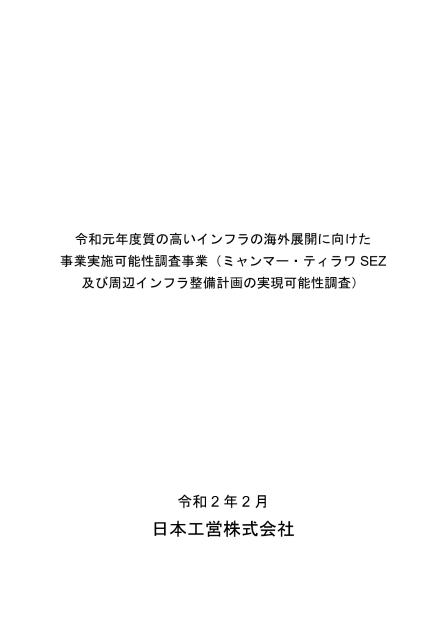令和元年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業(ミャンマー・ティラワSEZ及び周辺インフラ整備計画の実現可能性調査)
報告書概要
この報告は、ミャンマー・ティラワ経済特別区(SEZ)及び周辺インフラ整備計画の実現可能性について書かれた報告書である。ティラワSEZは日本とミャンマーが官民一体で開発を進める工業団地プロジェクトであり、当初想定以上の好調な進捗を見せている。早期開発区域のZone A(370ha)に加えて次期開発区域のZone B(260ha)の開発も順次進み、契約済み企業は100社を超えている状況となっている。また日本政府の円借款により、ティラワ発電所、送電線、通信改善、ティラワ港コンテナターミナル、アクセス道路、ラグンビン浄水場からの配水、新バゴー橋等のインフラも稼働・建設中である。
しかしながら、SEZ全体開発(2,900ha)に向けては基礎インフラの整備遅れにより、近い将来における水不足、電力不足、交通渋滞、洪水被害といったSEZ発展の障害が憂慮される状況である。既存の2016年JICA報告書は土地利用計画が中心でインフラ整備内容が少なく、その後の新規ODA事業開始や土地利用計画変更により不十分となっている。本調査では、ティラワSEZ全体開発に必要な基礎インフラを調査し、事業成立可能な整備計画策定を目的として実施された。
調査内容として、既往開発・調査の整理、周辺インフラの現状及び将来計画整理、土地利用計画検討、需要予測・計画策定、スケジュール及びコスト試算、事業計画策定が行われた。財務分析の結果、公共性の高い変電所、クリーク拡張及び調整池等の洪水対策、外周道路を公共事業とすることで、民間事業として14.0%の内部収益率が見込まれ実施可能性が確保できることが判明した。全インフラを民間事業とした場合は内部収益率5.3%となり実施可能性は極めて厳しいため、官民連携による適切な役割分担が重要である。今後のSEZ開発では、工業エリア拡張、住宅商業エリア開発、港湾との一体開発、スマート化、インフラ開発という5つの開発レイヤーでの総合的推進が必要であると提言されている。