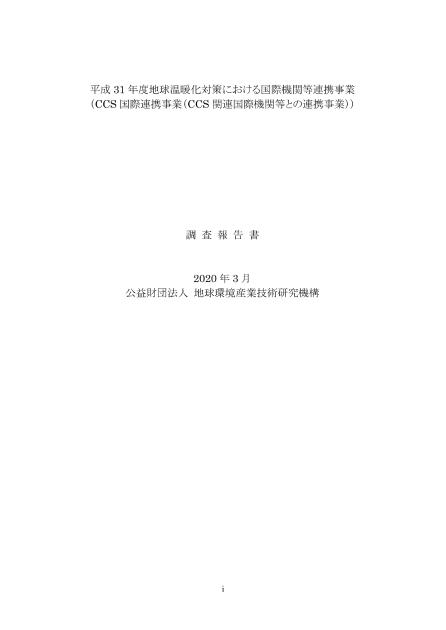平成31年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業(CCS国際連携事業(CCS関連国際機関等との連携事業))調査報告書
報告書概要
この報告は、平成31年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業について書かれた報告書である。
本事業では、CCS(二酸化炭素回収・貯留)に関する国際機関との連携と規格化対応を実施した。CSLFとIEAGHGという主要な国際機関の活動に参加し、CO2の海底下貯留に関係するロンドン条約会合の動向調査を行った。各国のCCSプロジェクト動向、助成制度、法制度の整備状況を調査し、経済産業省に適宜報告した。
CSLF技術グループでは、2017年版技術ロードマップのフォローアップが本格化し、2021年版の策定が決定された。PIRT制度の認定プロジェクトスキームへの特化、「孔隙利用の改善」「CO2ハブ・インフラストラクチャ」「エネルギー多消費産業CCS」各タスクフォースの報告書発行、新規活動計画の検討などが進められた。
IEAGHGでは2019年度に14件の報告書が発行され、新たに10件の技術研究が開始された。第5回燃焼後回収国際会議をRITEが共催し、日本企業の技術アピールの良い機会となった。ロンドン条約では、海底下地中貯留を目的としたCO2輸出を可能とする改正の暫定的適用が合意され、多国間プロジェクトの実施が可能となった。
CCUSイニシアティブでは産業界との連携強化が進み、米国では2,500万トン/年から5億トン/年への拡大ロードマップが発表された。中国は2050年に8億トン/年以上の大規模普及を目指すロードマップを策定した。欧州では英国が8億ポンド以上のCCSインフラストラクチャ基金を創設し、オランダでは新たなインセンティブスキームSDE++が開始された。大規模プロジェクトでは、豪州のGorgonプロジェクトがCO2圧入を開始し、ノルウェーとオランダのプロジェクトも最終投資決定を予定している。
G20向けCCUS国際協力強化提言のフォローアップにも取り組み、主にエネルギー・環境大臣会合の閣僚声明とアクションプランに反映された。規格化対応では、ISO/TC265の活動に対処するため国内審議委員会と5つのワーキンググループを設置し、第13回総会への専門家派遣と規格開発への積極的参加を行った。各国の規格化動向把握のためヒアリング調査も実施し、CCS関連規格の国際標準化を推進した。