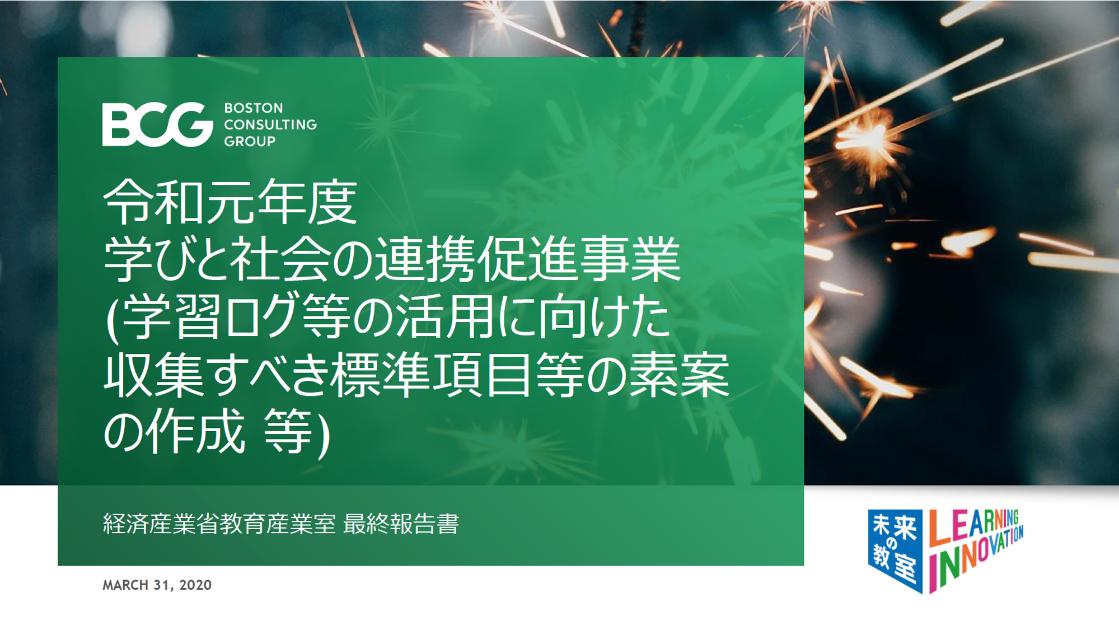令和元年度学びと社会の連携促進事業 (学習ログ等の活用に向けた収集すべき標準項目等の素案の作成等)最終報告書
報告書概要
この報告は、学習ログ活用のグランドデザインについて書かれた報告書である。
2019年6月に示された「未来の教室」ビジョンでは、学びのSTEAM化、学びの自立化・個別最適化、新しい学習環境の構築という3つの柱が掲げられた。従来は教育現場のデジタライゼーションの遅れが教育改革のボトルネックとなっていたが、GIGAスクール構想により1人1台PCが実現される機運が高まり、このボトルネックが一気に解消される状況となった。
このタイミングで学習ログの在り方について議論し、関係省庁も巻き込みながらロードマップ・アクションプランを策定することで、目指す学びの実現に向けた具体的な道筋をつけることが背景となっている。本検討のゴールは、学習ログ活用のグランドデザインを策定し、2030年を想定した目指す姿と2020年から2030年にかけてのロードマップを作成することである。
2030年の目指す姿として、学習者は個別学習計画を立てて自律的に学べるようになり、ログをもとにしたリフレクションやリコメンドを通じて自己調整学習が実現される。教員の役割はteacherからcoachへとシフトし、一斉授業から個別学習へ比重が移行する。学習者一人一人の興味・関心・到達度が見える化され、ギフテッドや2Eなど発達に特徴がある子供への対応も含めて「落ちこぼれ」「吹きこぼれ」の把握とケアが容易になる。多様な学びが選択可能となり、ログを通じて学びの質が担保されることで、教室を前提としない多様な環境での学習が実現され、不登校問題の根本解決にもつながる。
教育者にとっては業務が効率化され、出欠や成績登録、各種アンケート回答が自動化・簡便化される。エビデンスに基づいたより良い学びの提供が可能となり、教員の経験値にデータに基づく科学的視点が加わった再生産可能な良質な授業が実現される。行政・研究者においては、幅広く精緻なビッグデータを活用したEBPMや研究が可能となり、質の高い学習データに基づいた研究の実現が期待される。