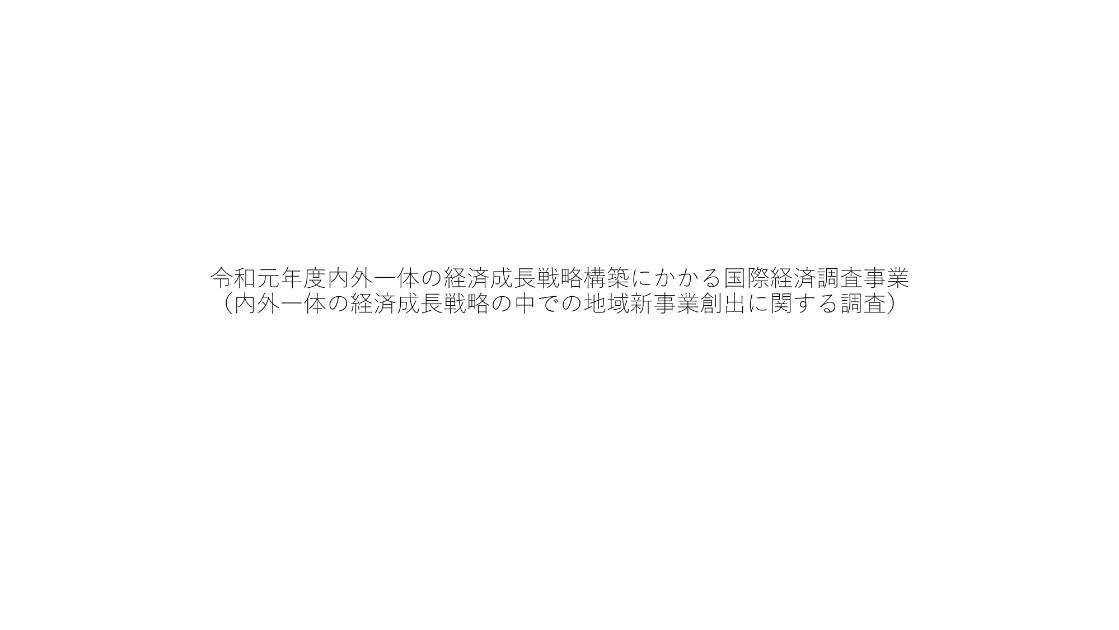令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(内外一体の経済成長戦略の中での地域新事業創出に関する調査)
報告書概要
この報告は、大学等研究機関における技術シーズを活用した研究開発型ベンチャーの創出に関する調査について書かれた報告書である。地域における新事業創出の課題として、大都市圏と異なりグローバル経済との接点や地元需要が限定的であることが挙げられているが、大学等の研究機関には様々な技術シーズが存在し、これらの事業化に成功すれば地域においてもグローバルな新事業創出が可能であることが示されている。本調査では、技術シーズを活用した新事業創出における成功要因を明らかにするため、大学等研究機関の組織設計に着目し、成功要因と実現に向けた課題を洗い出している。
研究開発型ベンチャーの成長過程における阻害要因として、大学の組織や制度構造に問題があるという仮説を設定し、研究所所属者が法人を設立して共同研究やライセンス契約を結ぶケース、未承継知財を活用するケースなど3つの具体的事例を調査対象としている。調査手法としては、国立大学6機関、私立大学1機関、国立研究開発法人1機関の計8機関にヒアリング調査を実施し、意思決定フロー、株式保有、役職就任、報酬規定、兼業時間・場所、共同研究締結窓口、知財関連事項、設備貸与などの項目について詳細な分析を行っている。
調査結果として、大学発ベンチャー認定制度の有無によって意思決定フローに変化があることが明らかになり、認定制度がある場合とない場合の2つのパターンでフロー図が作成されている。各大学において複数の部門と複数の規約での精査を経て意思決定が行われるため、関連規約への理解が不足している場合、想定通りに研究開発型ベンチャーの創出が行われないケースが懸念として挙げられている。特に、兼業規則、利益相反マネジメントガイドライン、共同研究関連規約、知財関連規約などが複雑に絡み合うため、個別ルールに基づいた判断により結果として研究開発型ベンチャーの成長を阻害する問題が発生することが指摘されている。
利益相反マネジメントについては、多くの大学で理解している職員が少なく、制度を厳格に運用するとベンチャーが稼働できないという懸念があることが明らかになっている。また、明確な利益相反行為の定義がないため、相談を受けた際に全てグレーと判断せざるを得ない状況や、大学職員がベンチャー創出を支援する際のインセンティブがなく、問題発生時のリスクが高いため常にディフェンス目線で対応してしまう課題が浮き彫りになっている。一方で、制度上明確な線を引いて遵守し、情報公開を徹底的に行うことで機能している大学組織の事例も報告されている。組織的利益相反を防ぐ体制構築のためには、情報公開のタイミングを学内で定め、漏れのない情報公開を行う体制を築くことが重要であると結論づけられている。