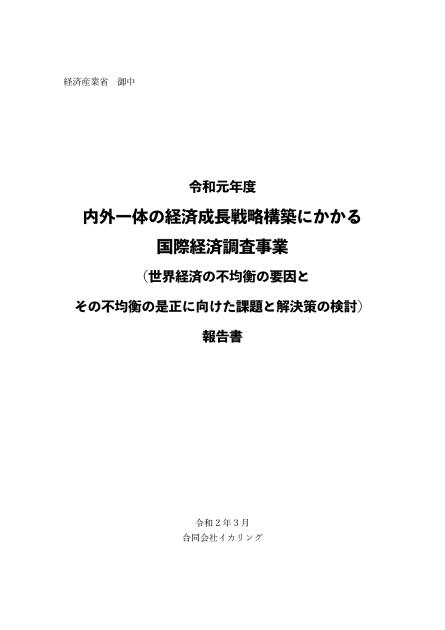令和元年度内外一体の経済成長戦略構築に係る国際経済調査事業(世界経済の不均衡の要因とその不均衡の是正に向けた課題と解決策の検討)調査報告書
報告書概要
この報告は、世界経済の不均衡とその是正に向けた課題について書かれた報告書である。グローバリゼーションが進展する中で、人口の都市部への集中やイノベーション産業の地理的集積が進み、デジタル経済においてはシリコンバレーや深センなどの特定地域に価値創造が集中している。金融面ではドル依存が拡大し、アルジェリアとブラジルのような国家間でもドル建て取引が行われるなど、ドルの基軸通貨としての地位が強化されている。外貨準備においてもドル保有が支配的であり、アジア通貨危機を経験したアジア諸国は特にドル準備を増加させる傾向にある。これらの現象は勝者総取りの経済構造を強化している。
世界の経常収支不均衡は近年縮小傾向にあるものの、構造的な問題が残存している。中国は急速に経常収支の均衡に向かい、産油国は資源価格変動の影響を受けながらも概ね黒字を維持している。ユーロ圏はドイツを中心とした大幅な黒字地域となり、アジア先進国も黒字を拡大している一方で、米国は依然として世界最大の赤字国である。これらの不均衡は国内の貯蓄投資バランスの変化と密接に関連している。
報告書は先進国の日本化現象を分析し、高齢化、低出生率、低インフレ、低金利、高い公的債務などの指標を用いて各国の状況を評価している。新興国では新しい経済ダイナミズムが見られ、メガシティの形成やユニコーン企業の誕生など、イノベーションの新たな源泉が生まれている。中国は中進国の罠を回避しつつ発展を続けているが、今後のリスクも存在する。
1930年代の長期停滞と現代の状況を比較分析し、人口動態の変化、技術進歩の停滞、投資の落ち込みといった共通点を指摘している。当時の対応策として大規模公共事業、金融緩和、互恵的自由貿易の推進が実施された。現代への教訓として、グローバリゼーションの後退が経済悪化を招く危険性を警告する一方で、適切な政策対応により長期停滞からの脱出は可能であると結論づけている。