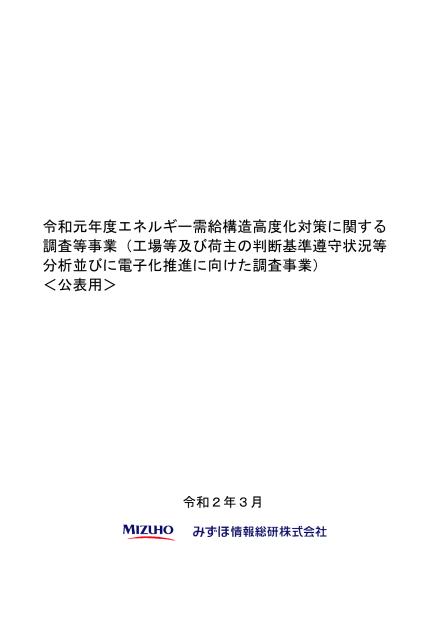令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(工場等及び荷主の判断基準遵守状況等分析並びに電子化推進に向けた調査事業)調査報告書
報告書概要
この報告は、令和元年度におけるエネルギー需給構造高度化対策に関する調査事業について書かれた報告書である。
本調査では、省エネ法に基づく特定事業者約12,000社および特定荷主約800社から提出される定期報告書および中長期計画書の電子化作業と分析を実施し、わが国の省エネルギーの現状把握および省エネ推進のための検討に資するデータを作成した。現在の省エネ法定期報告の執行体制については、基本的に人手が介在したフローとなっており、電子報告システムが用意されているものの、過去からの慣例により紙媒体での申請が継続されているほか、PDF形式での提出により電子データとしての活用ができない形での報告が存在するため、電子化作業により再度文字データを作成する非効率な作業フローとなっている。
事業者クラス分け制度については、約6割の事業者が努力目標を達成してSクラスを取得しており、このうち半数程度が5年度間平均エネルギー使用原単位の1%改善を達成している。エネルギー使用原単位の改善を達成している事業者の大半は通常のエネルギー使用原単位と電気需要平準化のエネルギー使用原単位の双方を達成している。ベンチマーク制度については区分間で達成状況に偏りがあり、達成事業者が存在しない区分から約半数程度の事業者が達成している区分まで存在する。ベンチマーク達成事業者においては約半数がエネルギー使用原単位の5年度間平均での1%改善を達成していないことから、先進事業者の救済措置となっているものと考えられる。
中長期計画書の記載については、目標部分の達成を意識した記載が望ましいものの、年平均1%の削減ができないような内容の記述を行っている事業者が存在するほか、「特になし」との回答や様式間の記載内容混同も散見され、制度理解が十分でないことが判明した。認定管理統括事業者による報告は初年度となる今年度で21者から報告があったが、制度理解が十分でないことから今後も丁寧な説明が必要である。特定荷主については報告数は例年同様800社程度であったが、統計的処理が可能な事業者数に満たないことに加え、母集団の適切性も判断できない状況であり、優秀事例の判定も困難な状況となっている。これらの課題解決には執行フロー全体での一貫した確認思想の整備と電子化への移行が急務であると結論づけられている。