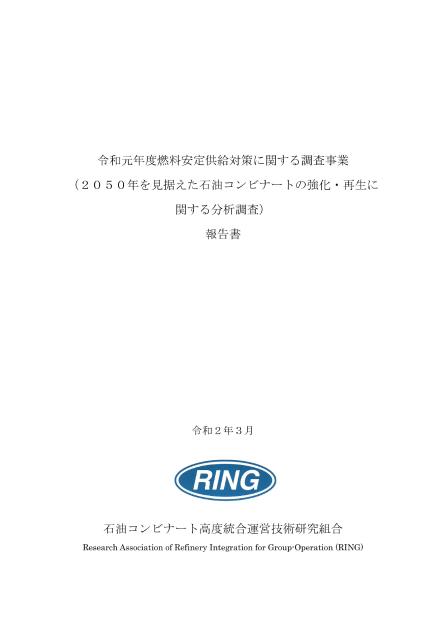令和元年度燃料安定供給対策に関する調査事業(2050年を見据えた石油コンビナートの強化・再生に関する分析調査)報告書
報告書概要
この報告は、2050年を見据えた石油コンビナートの強化・再生に関する分析について書かれた報告書である。
日本の石油需要は減少傾向にある一方、世界的には石油需要が拡大し続ける見通しの中、国際競争の激化により石油・石化製品の輸入圧力が高まることが予想される。このような状況下で、日本の製油所の国際競争力を維持・強化し、石油・石化製品の安定供給を将来にわたって確保することが必要不可欠である。
本調査では、AHP(階層化意思決定法)を用いて国内外25の主要コンビナートの競争力評価を実施した結果、RING事業による企業間連携・高度統合により日本のコンビナートは競争力を向上させているものの、アジアの競争力上位コンビナートとの差は拡大する方向にあることが判明した。日本の石油産業を中心としたコンビナートは、高付加価値設備の活用や増強による設備最適化、石化シフトの拡大、輸出能力の大型化、共同輸出基地の構築等を通じて、新たな統合運営や広域連携により効率化を進めることが重要である。
中国における石油精製能力は、パラキシレン不足の需給バランス解消のため大手民間企業を中心とした大規模製油所建設が継続され、原油からパラキシレン、ポリエステルまでの一貫生産体制が強化される見通しである。この結果、石油精製能力の余剰は解消されず、ガソリンや軽油のアジア市場への流出が増加する方向にある。日本における石化シフトの柱であるガソリンC8留分のパラキシレン転換・輸出については、中国での大型パラキシレン新設を考慮し、コスト負担の大きい単独装置新設を避け、既存設備の能力増強や共同新設等の方策が有効である。
石精石化統合LPモデルを用いた2023年の需給試算では、現状の設備能力を維持しつつ2018年度実績並みの原油処理を行った場合、全国で約170千BD相当のTOP能力が余剰となり、輸出競争力強化、揮発油留分の石化シフト、重油分解設備の最大活用や能力増強が必要であることが明らかになった。特に瀬戸内地域では揮発油の余剰量が他地域と比較して多く、従来の2.5倍程度の輸出が必要となるため、大型出荷のための共同輸出体制構築や揮発油分の石化シフトが急務である。
循環型社会に向けた欧州石油コンビナートの調査では、2050年までの脱炭素化に向け、CO2を原料とする合成ガス生成技術の商用化、小規模製油所のバイオリファイナリーへの転換、廃プラスチックを原料とするRe-Oil技術の開発、再生可能エネルギーを活用したe-fuel等の次世代技術導入が進められている。これらの対応において、既存設備を容易に廃棄することなく事業環境の変化に応じて転用し新事業に活用していることが特徴的である。日本の石油コンビナートも類似した設備構成や環境を有しており、設備廃棄を避け、高価な反応塔等の付加価値の高い生産設備への転用が可能であり、様々な環境変化への対応が期待される。