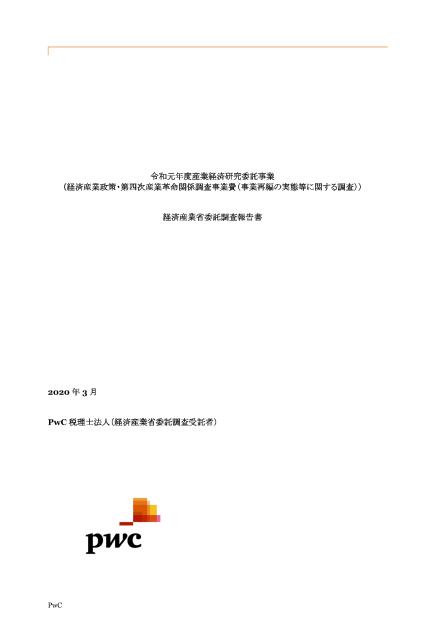令和元年度産業経済研究委託事業(経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費(事業再編の実態等に関する調査))報告書
報告書概要
この報告は、事業再編における近年の環境変化および海外の組織再編税制に関する混合対価要件について書かれた報告書である。経済産業省の委託により、PwC税理士法人が日米英独仏の5か国を対象として2020年3月に実施した調査である。
調査背景として、我が国企業を取り巻く経営環境の変化の中で事業再編の重要性が高まっているが、欧米諸国と比較して株式対価M&Aや混合対価の活用に制度上の課題があり、手法が限定されている現状がある。また、我が国のベンチャー企業は上場を選択する割合が高く、M&Aによる既存企業とのオープンイノベーションが進展していない状況である。
事業再編の傾向調査では、金融危機のあった2009年に案件数が大幅減少し、その後回復したが2015年頃をピークに減少傾向にあることが明らかとなった。日本は国内企業間の買収取引の割合が高いが、海外企業とのM&Aが増加傾向にある。対価の種類については、全体的に現金対価の取引が増加しているものの、案件規模が大きくなるほど株式対価・混合対価の割合が高くなる傾向がある。日本では諸外国と比較して株式対価による取引の割合が極めて低い状況である。
海外税制調査では、米国の適格組織再編制度は類型ごとに異なる要件があり理論的一貫性に欠けるが、実務上は柔軟な非株式対価を許容する類型を選択することで対応している。英国では株式交換等において非株式対価の制限がなく、株主の対象会社に対する資本関係に実質的変更がないことを課税繰延の根拠としている。ドイツでは事業の現物出資と株式交換において、出資対象資産の簿価の25%または50万ユーロを上限として非株式対価の利用を認めている。フランスでは組織再編行為において、非株式対価がA社株式額面総額の10%以内であれば課税繰延を認めている。
株式対価M&A事例調査では、米英独仏から合計10件の事例を選定し分析した結果、買収資金を賄う手元資金がない場合に外部借入によらず株式対価を活用するケースが多く見られた。これらの調査結果を踏まえ、我が国の組織再編税制における課題と制度見直しの方向性について検討が行われた。