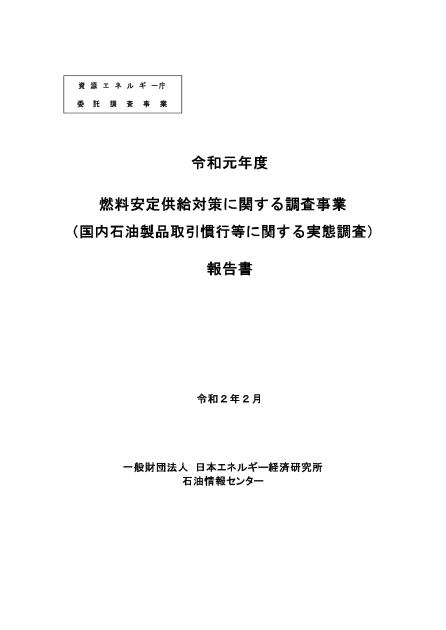令和元年度燃料安定供給対策に関する調査事業(国内石油製品取引慣行等に関する実態調査)報告書
報告書概要
この報告は、令和元年度における国内石油製品取引慣行と輸入石油製品の流通実態について調査した報告書である。資源エネルギー庁委託により日本エネルギー経済研究所石油情報センターが実施し、ガソリン適正取引慣行ガイドライン策定後の石油製品市場の変化を分析している。2019年にはガソリン輸入量が258万KLに急増し、内需に占める輸入比率が5.2%に達した。これは元売の事業再編により非系列向け業転玉の供給が減少したため、商社や広域特約店が製品輸入を活発化させたことが主因である。シンガポール市場でのガソリン価格低下も輸入増加を後押しした。税関別分析では、堺、名古屋、金沢、下関、呉、苫小牧の6地域が主要な輸入拠点となっており、特に堺と名古屋が全国輸入量の大部分を占めている。アンケート調査では、77%の販売店が事後調整を受けておらず、仕切価格の事後的な修正は限定的である。系列外取引については80%の販売店が業転玉を購入しておらず、業転玉の取引環境は厳しくなっている。過度な安売りについては40%が減少したと感じており、価格競争の激化に一定の歯止めがかかっている。経営面では人手不足が深刻で、69%の販売店が人材確保に課題を抱えている。地下タンクの流出防止対策は49%で措置済みだが、期限の迫る店舗も存在する。輸入石油製品の流通実態と国内市場への影響、取引慣行の変化を包括的に分析し、石油製品市場の構造変化を明らかにした調査となっている。