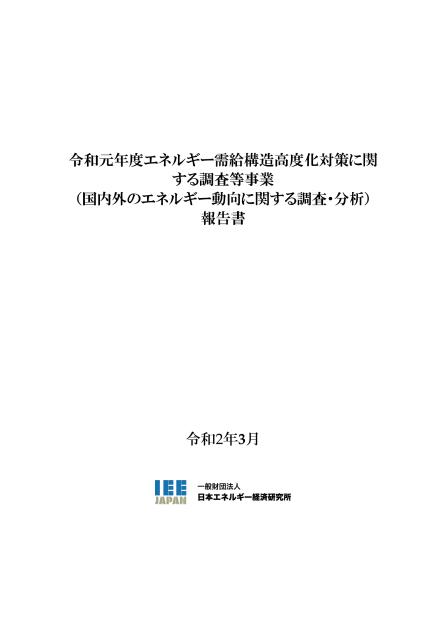令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(国内外のエネルギー動向に関する調査・分析)報告書
報告書概要
この報告は、令和元年度における日本の国内外エネルギー動向について包括的に分析した調査報告書である。
日本のエネルギー消費は1970年代の高度経済成長期にGDPを上回る伸び率で増加したが、二度の石油ショックを契機として製造業を中心とした省エネルギー化が進展し、エネルギー消費を抑制しながら経済成長を実現した。2018年度の最終エネルギー消費は気温上昇による暖房需要減少により前年度比2.9%減少し、部門別では産業部門62.6%、運輸部門23.4%、家庭部門14.0%の構成となっている。エネルギー効率については、1973年度の73PJ/兆円から2018年度には37PJ/兆円へと大幅に改善し、国際比較においても日本は世界最高水準の効率性を維持している。
エネルギー供給構造では、1973年度に75.5%を占めていた石油依存度が2018年度には37.6%まで低下し、石炭25.1%、天然ガス22.8%への多様化が進んだものの、化石燃料依存度は91.0%と依然として高水準である。東日本大震災後の原子力発電停止により化石燃料の輸入が増加し、エネルギー自給率は2014年度に過去最低の6.4%まで低下したが、再生可能エネルギー導入と原子力再稼働により2018年度は14.9%に回復した。石油の中東依存度は88.3%と高く、供給安定性に課題を抱えている。
国際エネルギー価格比較では、LNG価格において日本は原油価格連動方式により他国より高価格となり、アジアプレミアムが発生している。電気料金とガス料金も国際的に高水準にあり、燃料調達方法や国内輸送インフラ、人口密度等の要因が内外価格差を生じさせている。今後のエネルギー政策では、安定供給確保と経済性向上の両立が重要な課題となっている。