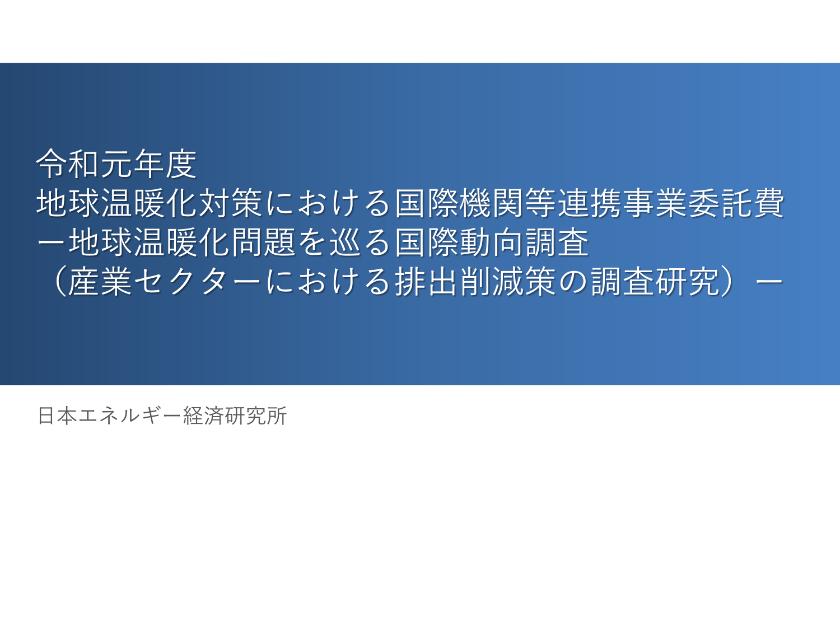令和元年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業委託費(地球温暖化問題を巡る国際動向調査(産業セクターにおける排出削減策の調査研究))
報告書概要
この報告は、炭素国境調整措置(国境炭素税)について書かれた調査報告書である。
EUは2019年にグリーンディールの一環として、気候中立の法制化、排出量取引制度の拡充、WTOルールと整合的な炭素国境税の導入などを含む5年間の政策パッケージを発表した。特に炭素国境調整措置については、2021年の法制化を目指し、生産がEUから野心の低い他国に移転するカーボンリーケージのリスクを低減するため、輸入品の価格に炭素含有量をより正確に反映させる仕組みとして提案された。マクロン大統領も製造業の環境対応要件の格差に対応するため欧州国境炭素税の必要性を訴えている。
米国では2021年の大統領選挙において、民主党のバイデン氏が炭素集約的な物品に対する炭素調整課税や割当制度について言及し、共和党系からも提案があるなど、党派を超えた関心の高い分野となっている。第116議会では複数の国境調整税法案が提案され、多くが輸入財への課税と国内輸出企業へのリベートを組み合わせた仕組みを採用している。
製品単位のGHG排出量算定については、温対法や省エネ法といった国内法、LCAやカーボンフットプリントなどの国際標準ISO、CDPやTCFDなどの自主取組による情報公開の枠組みが存在するが、データカバレッジの低さや不一致、公表データの利用可能性等の課題がある。特にEU-ETSのベンチマーク規則は、域内上位10%の閾値を示すものの、電力を含まず副生ガスの一部のみが算定されるため、日本の省エネ技術が不利に評価される可能性がある。
モデル分析によると、炭素価格や関税が課された場合の鉄鋼産業の相対価格上昇率は日本、EU、米国の順に大きくなり、特に報復関税が生じた場合には日本とEUへの影響が大きく、米国が優位になる結果が示されている。一方で、制度設計によってはGood Performerの生産を伸ばすことも可能である。
今後はEUの制度設計と米国大統領選挙の結果がポイントとなり、対象国や適用方法、カーボンコンテントの考慮など、公平かつ透明度の高い制度設計には実務的課題が多く残されている。