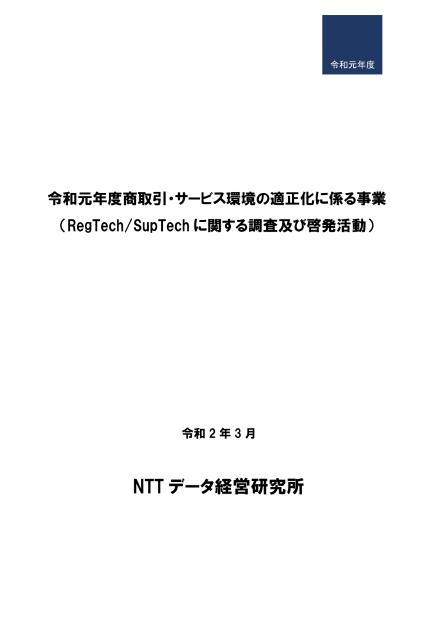令和元年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(RegTech/SupTechに関する調査及び啓発活動)
報告書概要
この報告は、RegTech/SupTechに関する海外動向調査と啓発活動について書かれた報告書である。RegTech/SupTechとは、民間事業者に課された規制業務や規制当局の監督・検査業務にテクノロジーを活用して効率化・高度化を図る取組である。日本では割賦販売法や商品先物取引法をはじめとする規制法分野において、諸外国ほど認知や取組が進んでいないことが前年度調査で判明した。
本報告書では、RegTech/SupTechエコシステムを「気づき」「対話」「試行」のサイクルを回しながら、ステークホルダー間の信頼とリスクマネーの供給を得て実際の導入に結び付ける一連のサイクルとして定義している。海外動向調査では、FSIのレポートによると39の金融規制当局のうち約半数が明確なSupTech戦略を策定済みまたは作成中であることが示されている。
英国では、Bank of Englandが「New economy, new finance, new Bank」において、デジタル経済への対応やカーボンニュートラル経済への移行も含む包括的な中長期目標を策定した。特に世界をリードするRegTechおよびデータ戦略の推進を優先分野の一つとして位置づけ、年間45億ポンドの規制報告費用の削減と高度化された監督による金融システムの強化を目指している。FCAも「Data Strategy」を公表し、データ駆動型の監督を目指した具体的な施策を示している。
米国では、OCCやCFPBがSandbox等の制度を通じて金融機関のイノベーション促進と自身の規制枠組みに対する新たな気づきの獲得を図っている。また、連邦政府と州政府の規制当局間での連携強化により、複雑な規制環境の整備が進められている。シンガポールでは、MASがAI原則「FEAT」を公表し、業界団体との対話を通じてAI適用のフレームワーク構築に取り組んでいる。
2019年度の特徴として、各国でAIの本格的な利用に向けた導入や監督の活動が活発化していることが挙げられる。今後、金融サービスの様々な分野でAIアルゴリズムの適用が進むことから、AI監督のあり方についてより具体的な議論の進展が期待される。