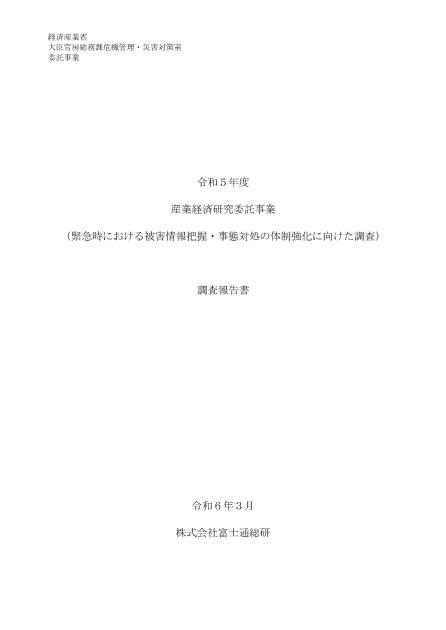令和5年度産業経済研究委託事業(緊急時における被害情報把握・事態対処の体制強化に向けた調査)調査報告書
報告書概要
この報告は、経済産業省における緊急時の被害情報把握と事態対処の体制強化に向けた調査について書かれた報告書である。令和5年度に株式会社富士通総研が委託を受けて実施した事業であり、首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模地震発生時における経済産業省の業務継続能力向上を目的としている。事業の背景として、今後30年以内に首都直下地震が70%、南海トラフ地震が70-80%の確率で発生するという予測があり、電気・ガス等のライフラインや産業界を所管する経済産業省の災害対応能力強化が急務となっている状況がある。
事業内容は主に2つの柱から構成されている。第一に大規模地震を想定したブラインド型シミュレーション訓練の実施であり、夏期と冬期の計2回の訓練を予定していた。夏期訓練は新任の防災担当官を対象とした首都直下地震想定の訓練として令和5年10月3日に実施され、危機意識の醸成と現行マニュアルの基礎的理解を目的として、ワークショップ形式で官房対策PT、エネルギーPT、物資PTの3つのチームが参加した。しかし冬期訓練については、令和6年1月1日に発生した能登半島地震の対応により参加者の多くが実災害対応に従事することとなったため中止となった。
第二の柱である経済産業省の危機管理・災害対策における課題の調査・分析では、夏期訓練の振り返りと能登半島地震対応のナレッジ取りまとめを実施した。能登半島地震の対応経験から得られた改善点として、派遣用装備品の拡充、マニュアルの整備・見直し、基礎知識集の作成、現地リエゾン専用メールアドレスの付与、進捗管理方法の整備、Teams活用訓練の実施等が抽出された。また現地リエゾン派遣者向けには、個人装備品の共有、現地リエゾン用マニュアルの作成、リエゾン向け訓練やシステム操作訓練の実施等が提言された。
今後の進め方として3つの重要な提言が示されている。まず現地リエゾンの支援体制について、個人の才覚に依存する現状から組織的な活動環境の整備が必要であり、県庁リエゾンが各市町村リエゾンを束ねる体制や現地支援本部の設立等が提案されている。次に情報管理の方法について、Teams上でのチャネル乱立による混乱を解決するため、正式ルートから担当者間直接連携への段階的移行と部署単位チャネルの活用が推奨されている。最後に物資支援における民間事業者の活用について、自治体職員による物資集積拠点運営の限界を指摘し、荷捌きや在庫管理に精通した民間事業者への委託による効率化が提案されている。