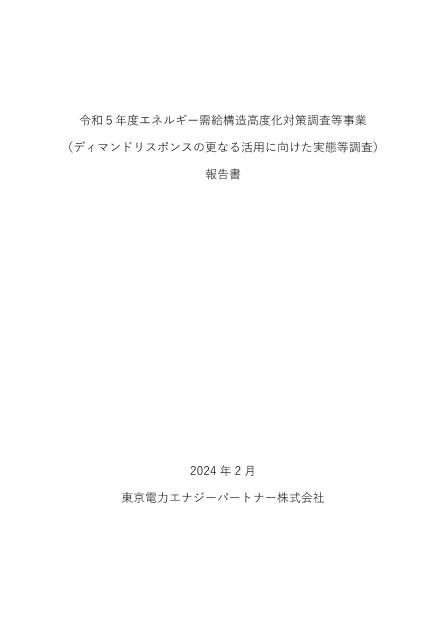令和5年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(ディマンドリスポンスの更なる活用に向けた実態等調査)報告書
報告書概要
この報告は、ディマンドリスポンス(DR)の更なる活用に向けた実態調査について書かれた報告書である。需給調整市場において三次調整力の応札不足が続く中、2024年度からの一次・二次調整力の取引開始に向けて、需要側リソース(DSR)の高度な制御技術を活用した市場参入が求められている。特に、オフライン枠の調達上限値が一次平常時必要量の全量まで引き上げられることにより、安定供給マインドを持つ事業者による調整力の更なる供出が必要となっている。本調査では、水電解設備と蓄電池を対象とした自動化制御の実証を行い、山梨県の米倉山サイトと山口県のトクヤマサイトにおいて実機テストを実施した。水電解設備については、PEM型とアルカリ型の両方で自動化制御を検証し、一次調整力への応動能力を確認している。自動化システムの構築には、制御・監視・管理ロジックの知識を有するハイスペックなエンジニアが必要であり、通信仕様の調整や事前テストなど相応の労力とコストが発生することが判明した。DR活用可能設備の見通し調査では、水素基本戦略に基づく2030年134GWの世界水電解装置導入目標を踏まえ、国内では2040年に14,100MWの電解型水素製造設備が導入される見込みである。蓄電池については、業務・産業向けで自治体施設、工場施設、文教施設を中心に導入が進み、2040年には929MWhの導入が予測される。結論として、カーボンニュートラル実現と安定供給の両立には、応答性に優れるPEM型水電解を一次調整力向け、大容量化が可能なアルカリ型を三次調整力向けとして活用することが望ましく、同様に蓄電池についてもリチウムイオン電池を一次調整力、NAS電池を三次調整力として活用することが提言されている。