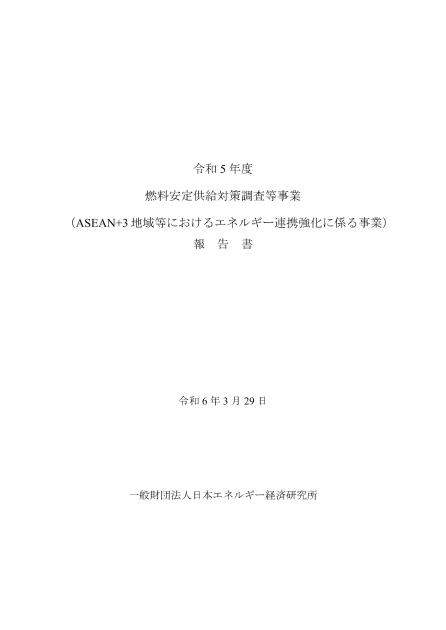令和5年度燃料安定供給対策調査等事業(ASEAN+3地域等におけるエネルギー連携強化に係る事業)報告書
報告書概要
この報告は、ASEAN+3地域におけるエネルギー連携強化について書かれた報告書である。令和5年度における日本エネルギー経済研究所による調査事業として、経済産業省資源エネルギー庁の委託を受けて実施された。
ASEAN+3地域は世界経済の重要な位置を占めており、2022年における世界GDP比は27.4%に達している。同地域では経済発展に伴い石油需要が増大し、中長期的には石油輸入量の大幅な増加が予想される状況である。COVID-19パンデミックにより一時的にエネルギー需要が減少したものの、令和3年度以降は各国でエネルギー需要がパンデミック前の水準に戻りつつある。
エネルギー概況について、ASEAN+3地域の一次エネルギー消費量は2021年で5,108Mtoeとなっており、2011年から2021年にかけて年平均2.5%の成長を記録した。エネルギー構成では石炭が32.7%、石油が26.3%、天然ガスが19.5%を占め、再生可能エネルギーは19.1%となっている。将来予測では2050年に5,499Mtoeまで増加する見通しである。
本事業では令和5年度に9回の会合やワークショップが開催された。主要なものとして、インドネシアで第24回SOME-METI協議、第22回SOME+3エネルギー政策理事会、第20回ASEAN+3エネルギー大臣会合、第17回東アジア首脳会議エネルギー大臣会合が実施された。また、ラオスでは石油備蓄ロードマップワークショップ、石油市場・天然ガスフォーラム、エネルギー安全保障フォーラムが開催された。これらの会合では政府関係者のみならず、エネルギー関連企業や研究機関の民間有識者が参加し、地域間のエネルギー連携強化に関する議論と情報共有が促進された。