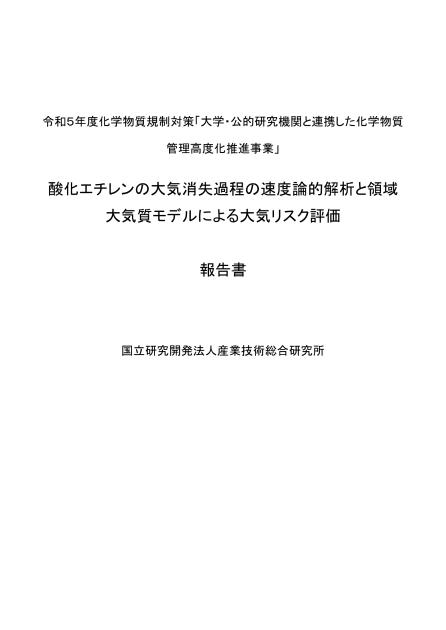令和5年度化学物質規制対策「大学・公的研究機関と連携した化学物質管理高度化推進事業(酸化エチレンの大気消失過程の速度論的解析と領域大気質モデルによる大気リスク評価)」報告書
報告書概要
この報告は、酸化エチレンの大気中における動態と健康リスク評価について書かれた報告書である。産業技術総合研究所と東京大学が連携して実施した令和5年度の化学物質規制対策研究の成果をまとめたものである。
酸化エチレンは特定第1種指定化学物質であり、合成材料や界面活性剤の原料、医療機関での滅菌剤として広く使用されているが、発がん性が指摘されており、環境省の指針値を上回る濃度が各地で観測されている問題がある。米国環境保護庁も同様の懸念を示しており、国内外において緊急性の高い課題となっている。
研究は3つのサブテーマで構成されている。第1のサブテーマでは量子化学と遷移状態理論を用いて酸化エチレンの大気化学反応速度定数を算出し、第2のサブテーマではPRTRデータに基づく国内排出インベントリを整備して領域大気質モデルCMAQによる大気濃度評価を実施した。第3のサブテーマではスモッグチャンバー実験により理論計算の妥当性を検証している。
排出インベントリの解析により、酸化エチレンの国内総排出量は届出排出量144トン、届出外排出量14トンと推計され、人口密集地である東京、大阪、愛知を中心とする地域で高い排出量を示した。領域大気質モデルによる計算では、関東地域において埼玉県南部で特に高濃度となり、これは東日本滅菌センターからの大量排出が原因であることが判明した。
計算結果では埼玉県の複数地点において米国環境保護庁の発がん性リスク基準濃度を上回る値が示され、仮に排出量を0.2倍まで削減しても高濃度地域では依然としてリスク濃度を超える可能性が示唆された。ただし、モデル計算値は観測値を2倍から10倍程度過小評価する傾向があり、未考慮の排出源やバックグラウンド濃度の影響が課題として残されている。
スモッグチャンバー実験では酸化エチレンとOHラジカルとの反応速度を測定し、量子化学計算による理論値との良好な一致を確認できた。しかし、酸化エチレンの定量分析において公定法による検出の不安定性が明らかとなり、分析手法の改良が今後の重要な課題である。