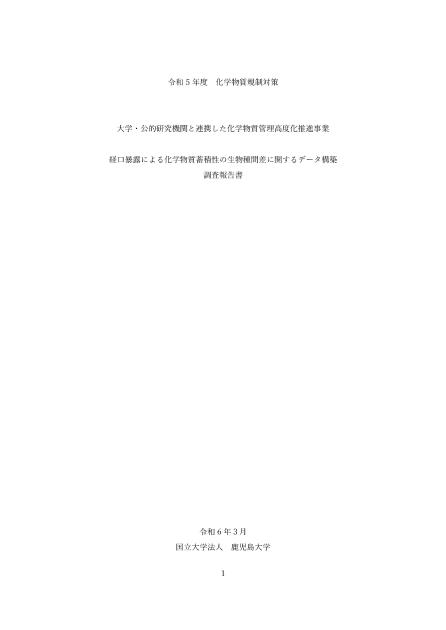令和5年度化学物質規制対策「大学・公的研究機関と連携した化学物質管理高度化推進事業(経口暴露による化学物質蓄積性の生物種間差に関するデータ構築)」調査報告書
報告書概要
この報告は、経口暴露による化学物質蓄積性の生物種間差について書かれた報告書である。鹿児島大学が令和5年度に実施した研究では、過去3年間にわたりコイを用いた経口濃縮試験を行ってきた継続研究として、ヒメダカを用いて生物種間差を検証することを目的とした。研究対象物質は、芳香族炭化水素類(テルフェニル類混合物)と紫外線吸収剤類混合物の2グループに分類され、それぞれ同時分析可能な物質群として設定された。流水式水槽を用いた経口暴露試験装置により、ヒメダカに対して餌料投与法による暴露試験を実施し、体内蓄積濃度を測定して生物濃縮係数(BMF)を算出した。試験の結果、芳香族炭化水素類ではトリフェニルメタン、トリフェニルベンゼン、o-テルフェニルのBMFが大きく、化審法の基準値0.007を超える結果となった。紫外線吸収剤類ではドロメトリゾールの低濃度区でのみBMFが基準値を超えたが、その他の物質の蓄積性は比較的小さい傾向が確認された。ヒメダカとコイのBMF比較では、芳香族炭化水素類の一部でヒメダカの方が10倍以上高い値を示し、紫外線吸収剤類では全般的にヒメダカの方が高い蓄積性を示した。しかし、種間差の大小はlogKowに依存せず、今後その要因解明が課題となっている。研究を通じて、化学物質の経口濃縮性評価において生物種間差が重要であることが明らかとなり、現行の化審法基準値BMF0.007は安全性の観点から妥当であると結論付けられた。