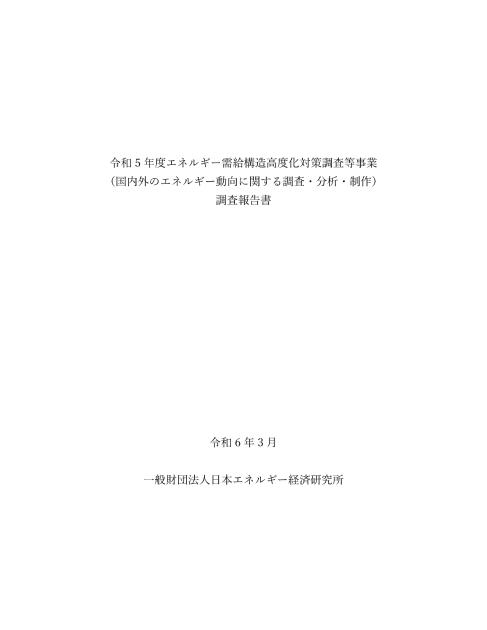令和5年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(国内外のエネルギー動向に関する調査・分析・制作)調査報告書
報告書概要
この報告は、令和5年度における日本の国内外エネルギー動向に関する調査・分析について書かれた報告書である。日本のエネルギー効率は実質GDP成長と密接な関連を持ちながら推移しており、過去数十年にわたって継続的な改善が図られてきたことが示されている。エネルギーバランス・フローの概要において、日本のエネルギー供給システムは石油・石炭・天然ガス等の一次エネルギーが発電・転換部門を経て最終消費者に届くという構造となっている。2022年度実績では、一次エネルギー供給を100とした場合、最終エネルギー消費は約65であり、発電や輸送過程で約35のエネルギーロスが発生していることが明らかとなった。一次エネルギー源別の流れを分析すると、原子力と再生可能エネルギーはその大部分が電力として消費され、天然ガスは電力と都市ガスの両方に転換されている。石油については電力転換の割合は限定的であり、主に石油精製を通じてガソリンや軽油等の輸送用燃料、灯油や重油、石油化学原料用ナフサとして利用されている。石炭は電力生成と製鉄用コークス原料としての使用が主要な用途となっている。LNG輸入価格の国際比較分析では、世界の天然ガス・LNG市場が北米・欧州・アジアの3つの主要市場で構成されており、各市場で価格決定方式が異なることが確認された。アジア市場では日本向け原油平均CIF価格にリンクした価格設定が7~8割を占める一方、欧州では各国の需給動向、米国と英国では国内取引地点での需給によって価格が決定されている構造となっている。