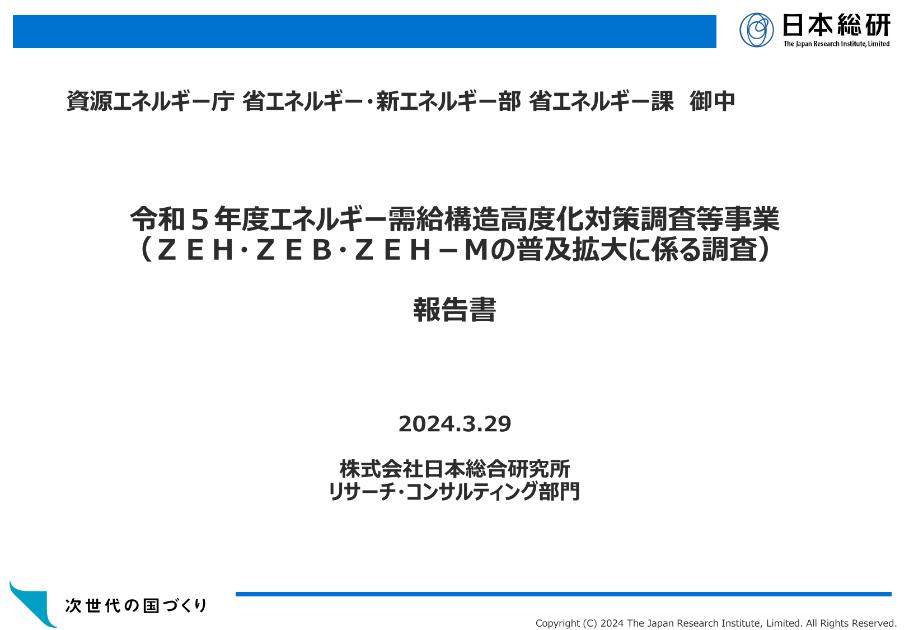令和5年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(ZEH・ZEB・ZEH-Mの普及拡大に係る調査)報告書
報告書概要
この報告は、令和5年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(ZEH・ZEB・ZEH-Mの普及拡大に係る調査)について書かれた報告書である。日本総合研究所がZEH・ZEB・ZEH-Mの普及拡大に向けた委員会運営と調査分析を実施した内容をまとめている。
ZEHフォローアップ委員会では、ZEHの普及状況分析を行い、事業者区分を細分化してハウスメーカー、大手・中堅ビルダー、デベロッパー、ビルダー・工務店の4区分でZEH化率を評価した。2022年度の新築住宅全体におけるZEH化率は23%に達し、ハウスメーカーは約7割まで普及が進んでいる一方で、大手・中堅ビルダーやビルダー・工務店は改善の余地が大きいことが明らかになった。
ZEH+の定義見直しでは、環境省令和4年度支援事業データを分析し、外皮性能基準を断熱等性能等級6以上に変更し、一次エネルギー消費量削減率を25%から30%に引き上げることが妥当と判断された。また選択要件についても、外皮性能を必須要件とし、自家消費拡大に貢献する機器設備を対象に含める方向性が示された。
ZEBビルダー/プランナー制度の見直しでは、現行制度では建築確認申請書の代表設計者以外は高評価を得られない課題や、割合のみの評価で供給量が反映されない問題を検討し、コンサルティングや改修も評価対象とする新たな区分案を提示した。
ZEB・ZEH-M委員会では、ZEBの普及状況として2022年度のBELS取得ZEBが約0.7%、ZEH-Mが戸数ベースで約24.4%であることを確認した。エネルギー消費量実績値の報告制度については、補助事業対象者に対するプラットフォーム構築案を検討し、BEMSによる運用時エネルギー消費量の用途別報告や建物運用情報の提出を求める方向性を示した。
未評価技術のWEBPRO反映に向けては、過年度の実証事業データを分析し、一定の省エネ効果を確認するとともに、評価の想定条件整理に関するガイドラインが2023年9月に公表されたことを報告した。設備容量の適正化については、ZEB設計ガイドラインのコラム更新案を検討し、現状課題整理や事例紹介を含める方向性を定めた。
ZEHデベロッパー制度見直しでは、太陽光発電設備の実績報告強化として搭載容量の追記や公表を行うこととした。集合ZEH設計ガイドラインについては、策定から3年以上経過し制度改正等により更新が必要となったため、温暖地における低層住宅を対象としたケーススタディの全面刷新とオーナー向け訴求資料の作成を行った。