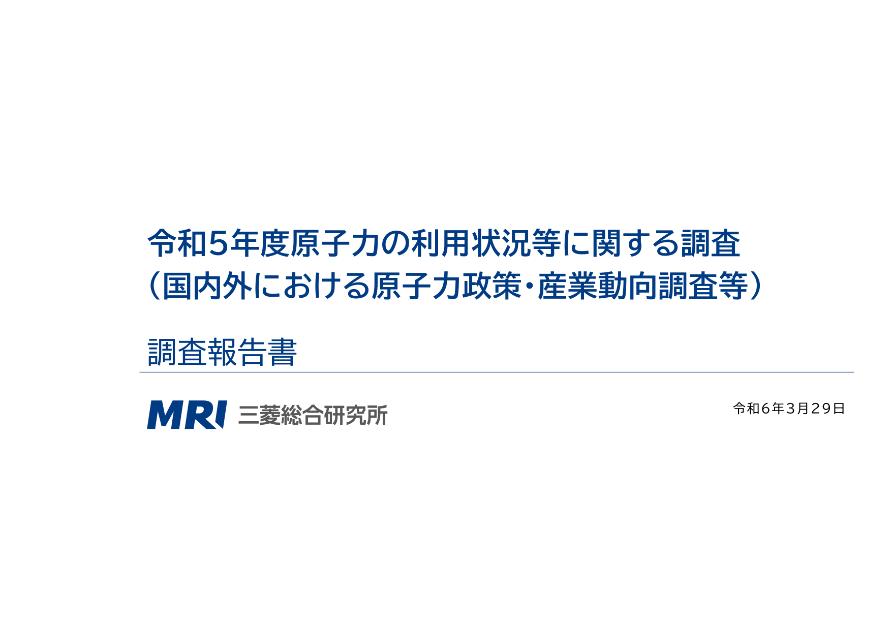令和5年度原子力の利用状況等に関する調査(国内外における原子力政策・産業動向調査等)調査報告書
報告書概要
この報告は、令和5年度における国内外の原子力政策・産業動向について包括的に調査・分析した報告書である。東日本大震災後の国内原子力産業の現状分析、諸外国の原子力政策動向、日本の原子力政策発信支援という3つの主要項目について調査が実施された。
国内原子力産業については、サプライチェーンの動向・市場調査、部品・素材の供給途絶対策、技術・人材の維持・強化の取組が詳細に分析されている。脱炭素への貢献では、原子力発電のライフサイクル温室効果ガス排出量が12gCO2e/kWhと極めて低く、石炭火力からのリプレイス価値の高さが確認された。また、三菱重工SRZによる再生可能エネルギーとの共存や水素製造の可能性、高温・高速炉による熱利用の脱炭素効果が期待されている。
海外では民間企業による先進炉導入事例が増加しており、ダウ社の高温ガス炉導入プロジェクトやマイクロソフト社のデータセンター向け原子力電力購入契約など、産業界での活用が拡大している。国内の産業動向では、原子力人材育成ネットワークを通じた産業界のニーズ把握と積極的な人材確保の取組が進められている。
原子力産業・サプライチェーンによる国内経済への裨益については、各国の経済効果や雇用創出が分析され、日本では原子力関係支出高として経済効果が測定されている。英国サイズウェルCプロジェクトでは供給確保と原子力パイプライン維持の非財務価値が重視されている。
日本の原子力国産化の歴史では、1960年代からの政府・電力会社・電機メーカーの協力関係により、国産化融資制度創設や技術移転を通じて島根原発で94%の国産化率を達成した経緯が示されている。革新炉の世界市場獲得ポテンシャルでは、EPR、AP1000、高温ガス炉、高速炉等において一定の競争力を有することが確認された。
諸外国の人材育成調査では、フランスの原子力職業大学とMATCHプログラムによる一気通貫した人材育成、米国の700社以上のサプライヤによる産業構築、英国の徒弟制度を活用したスキル標準化、韓国の2030年まで2万名のエネルギー人材育成目標などが詳述されている。他産業の人材育成では、デジタルスキル標準や蓄電池・半導体業界の取組事例が参考事例として整理された。最終的に、これらの調査結果に基づく日本国内の人材育成体制改善案の検討が行われている。