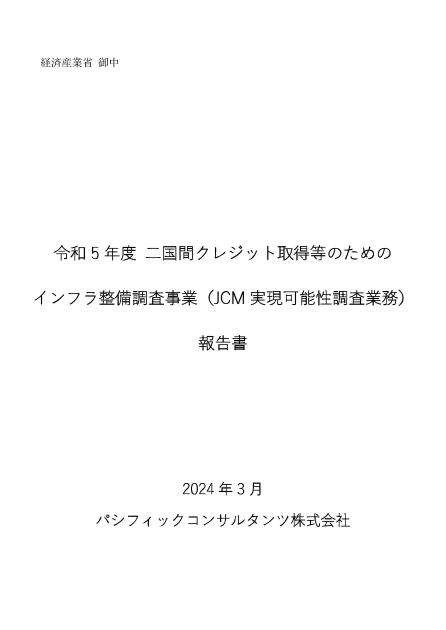令和5年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業(JCM実現可能性調査業務)報告書
報告書概要
この報告は、令和5年度の二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業について書かれた報告書である。
本調査事業は、パリ協定下での温室効果ガス削減目標達成に向けて、日本が途上国との間で二国間クレジット制度(JCM)を活用し、官民連携により2030年度までに累積1億トンCO2程度の国際的な排出削減量確保を目指すものである。JCMは優れた脱炭素技術等の途上国への導入を通じて実現した温室効果ガス削減・吸収量を評価し、日本の削減目標達成に活用する制度であり、現在29か国とパートナーシップを締結している。
事業の主要な実施項目として、まず我が国企業によるJCM実現可能性調査支援業務が挙げられる。これは一次・二次公募を通じて14件のプロジェクトを採択し、旭化成の繊維染色技術、AGCの苛性ソーダ製造プロセス転換、兼松のパーム油収率向上技術など、多様な分野での脱炭素技術導入の可能性を調査した。各事業者には進捗管理、調査支援、助言を提供し、中間報告会および最終報告会を通じて第三者有識者による評価を実施した。
次に、新規JCMプロジェクト組成に向けたポテンシャル案件調査として、ウズベキスタン、ブラジル、フィリピン、インド、UAEの5か国で現地調査とセミナーを開催した。各国の温室効果ガス排出状況、脱炭素政策、エネルギー事情を分析し、JCMプロジェクト化の可能性がある分野を特定した。ウズベキスタンでは省エネと再生可能エネルギー、ブラジルでは工業部門省エネと廃棄物発電、フィリピンでは製造業省エネと太陽光発電、インドでは工業省エネと水素・アンモニア分野、UAEでは太陽光発電と水素製造分野において高いポテンシャルを確認した。
さらに、JCM促進に係る調査事業として、実績に乏しい二酸化炭素回収・利用(CCU)分野とプログラム型プロジェクト分野について詳細調査を実施した。CCU分野では既存の方法論を分析し、JCMでの適用可能性を検討した。プログラム型プロジェクトでは、複数の小規模プロジェクトを統合管理する手法について、CDM、J-クレジット、VCSの事例を比較検討し、JCMへの適用における課題と提言をまとめた。
最後に、アジア・ゼロエミッション共同体での「JCM利活用促進に関する国際会合」を環境省と共催で開催し、AZECパートナー国の政府関係者が参加して今後のJCM利活用促進について議論した。
本事業を通じて、JCMの拡大に向けた具体的な道筋が示され、民間資金を中心とする大型プロジェクトの開発促進、新技術分野でのJCMプロジェクト化、パートナー国の拡大などの重要性が確認された。今後は2030年度の1億トンCO2削減目標達成に向けて、これらの成果を基に更なるJCMの推進と拡大が期待される。