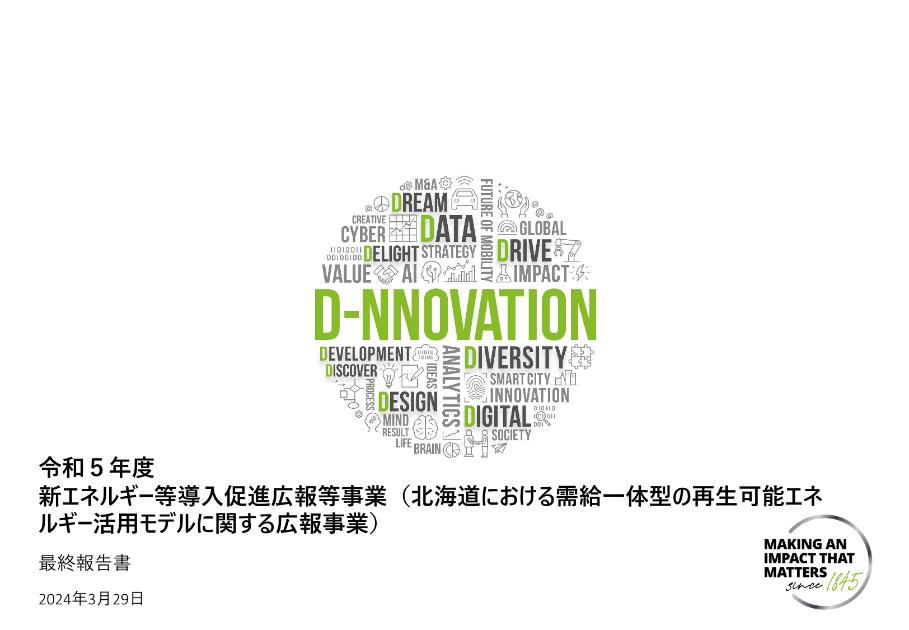令和5年度新エネルギー等導入促進広報等事業(北海道における需給一体型の再生可能エネルギー活用モデルに関する広報事業)最終報告書
報告書概要
この報告は、北海道における需給一体型の再生可能エネルギー活用モデルに関する広報事業について書かれた報告書である。北海道は広域分散・積雪寒冷という地域特性から、他地域と比較して自動車のガソリン由来のGHG排出量が多く、物流・交通分野の脱炭素化が急務となっている。しかし、寒冷地であることゆえのクリーンエネルギー自動車導入への懸念等からEV/FCV導入は進んでいない状況にある。
本事業では、物流・交通分野における再エネ・水素活用にフォーカスし、道内外の事業者に対するヒアリングを実施するとともに、全体イベントにて道内の物流・交通関連事業者への情報共有を行い、脱炭素に向けた機運醸成を図った。調査結果によると、商用利用の観点では、ラストワンマイル輸送のような短距離輸送向けにはEV、長距離輸送向けにはFCVの導入の可能性が高いことが明らかになった。EVは商用利用向けに導入が進むものの、充電時間が長く、航続距離が短いため、短距離輸送が中心となる。FCVは商用利用向けには実証段階であるが、充電時間が短く、航続距離がEVに比較して長いため、長距離での利活用が期待される。
EV特有の課題として「長い充電時間」「デマンド変化による電気料金の高騰」が挙げられたが、現在はカートリッジ式EVの実証が進められており、充電時間の短縮のみならずカートリッジを用いたデマンド調整も検討されている。また、EV/FCVの共通課題として挙げられた「寒冷地では始動性と電費性能の低下」は寒冷地用オプションの利用により軽減され、モビリティ側の寒冷地特有の課題は無いと主張する事業者も存在する。さらに、EV/FCVの共通課題として「経済性の不成立」が挙げられたが、充電ST向けには従量課金制度への移行、水素ST向けには値差支援等の政府対応により、今後の経済性の成立が期待される。道内における電動車の導入ポテンシャル推計では、道央21都市とその他人口の多い5都市の計27都市について推計を行い、将来の人口推計と共に保有車両数が減少していく中、保有車両数に占める電動車の割合は拡大し、物流部門においては小型トラックにはHV/EV/PHVの利用が、中・大型トラックにはFCV利用が特に期待されることが示された。