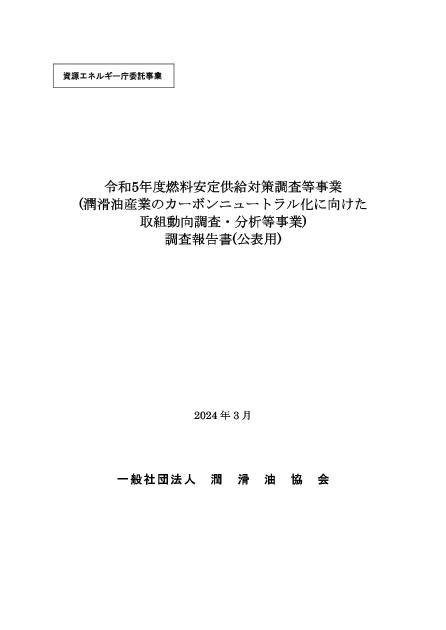令和5年度燃料安定供給対策調査等事業(潤滑油産業のカーボンニュートラル化に向けた取組動向調査・分析等事業)調査報告書
報告書概要
この報告は、潤滑油産業のカーボンニュートラル化に向けた取組動向調査について書かれた報告書である。資源エネルギー庁委託事業として、一般社団法人潤滑油協会が実施した令和5年度の調査結果をまとめたものである。
報告書は2部構成となっており、第1部では事業概要として、潤滑油産業におけるカーボンニュートラル化の課題と目的を説明している。2050年カーボンニュートラル実現に向け、潤滑油産業では従来の基油再生や低粘度潤滑油の利活用に加えて、新たな取組の拡充・加速化が求められている状況を示している。また潤滑油品質委員会を設置し、学識経験者、潤滑油製造事業者、自動車業界関係者等で構成する体制で事業を実施したことを述べている。
第2部の事業結果では、国内外の潤滑油産業における低炭素化・脱炭素化への取組状況を詳細に調査・分析している。国内調査では26社への アンケート調査を実施し、約7割の事業所が低炭素化・脱炭素化に取り組んでいることが判明した。取組理由として企業の社会的責任や顧客・市場からの要請が多く挙げられ、2050年カーボンニュートラルへの関心の高さが確認された。一方で、環境対応製品のコスト増加や基油・添加剤の入手性が課題として指摘されている。
カーボンフットプリント算出については、7割の事業所が取り組みたいと回答しており高い関心を示している。しかし実際の算出に関しては情報収集や業界基準策定の必要性が強く求められている。ロードマップ作成については4事業所が作成済みであるが、多くは情報不足により作成に至っていない状況である。
海外調査では、欧州のUEILが2023年10月に潤滑油・グリースの製品カーボンフットプリント計算方法論を公開し、米国のAPIも2021年から取組を開始して2023年5月に技術報告書を発行したことが確認された。アジアでは ALIAが各国団体と連携してサステナビリティに関する情報収集を行っている。
自動車パワートレイン動向では、日本自動車工業会が2050年において乗用車の60%が内燃機関搭載車になると予測していることから、今後も潤滑油の需要が継続することが示されている。EUでは2035年以降内燃機関車販売を原則禁止するが合成燃料使用に限り認める方針を決定し、米国でも当初のEV普及目標を緩和する動きが見られる。
第2章では超高粘度指数エンジン油に関する調査・検証結果を報告している。従来のエンジン油と比較して低温粘度が低く省燃費性に優れ、かつ高温でも内燃機関の信頼性を維持できる製品として、カーボンニュートラル移行期の低炭素化に貢献することが期待されている。海外ではACEAが低粘度SAE 0W-16エンジン油に特化したACEA C7-23カテゴリーを導入するなどの動きがある。国内では潤滑油業界と自動車業界が一体となり2025年以降の市場投入を目指して開発が進められている。